2025年5月8日

はじめに:政治コンテンツと「言論の岐路」
いま、政治や選挙に関する情報をネットで発信する人たちが増えています。YouTubeでは、政治家の発言をわかりやすく解説する動画や、選挙の裏側を追う解説コンテンツ、政策に関する持論を展開する政治系YouTuberたちが人気を集めています。X(旧Twitter)やTikTokでも、候補者の比較や、政治的な立場に基づく発信が日々投稿され、たくさんの反応を呼んでいます。
そんななか、最近話題になっているのが、GoogleやYouTubeによる「政治コンテンツの収益化オフ(無効化)」の方針です。これはつまり、政治や選挙に関連する発信に対して、広告をつけさせないという措置のこと。広告がつかない=収益が得られないわけですから、発信者にとっては死活問題です。
もちろん、広告主の側にも理由はあります。「過激な主張やフェイクニュースの横に自社の広告を載せたくない」という声が上がれば、プラットフォーム側としても「安全な環境を整える」必要があるわけです。ただ、その「安全」の基準があいまいだったり、一律に適用されてしまったりすることには、発信する側としてはやはり戸惑いがあります。
この「収益化オフ」の動きが象徴しているのは、いまネット上の政治的発信が大きな岐路に立たされているということです。かつては、マスメディアが情報を一方的に届ける時代でしたが、いまは誰でも自由に発信できる時代。政治の話をするのも、分析するのも、意見を述べるのも自由…そう思っていたはずが、広告という経済的要素が絡むことで、「何を発信していいのか」「どこまで許されるのか」が揺らぎはじめています。
「表現の自由」と「経済活動としての発信」のあいだには、もともと微妙なバランスがありました。個人が趣味で発信していた時代から、収益化が可能になり、プロ顔負けのチャンネルやアカウントが登場したことで、もはや「情報発信=仕事」になっている人も多い。だからこそ、「収益が止まる=発信できなくなる」現実もあるわけです。
いま問われているのは、政治的な発信における「中立性」ではなく、その発信が社会にとってどうあるべきかという本質です。偏っていてもいい、主張があってもいい。ただし、それを「お金にしていいのか?」という点で、プラットフォーム側の価値観と発信者の自由がぶつかり始めているのです。
このコラムでは、そんな「収益化オフ」の動きが示す問題の背景を掘り下げながら、SNSやYouTube、そして自前のウェブサイトなど、現代における政治発信のあり方を考えていきます。表現の自由と収益の自由、その線引きは誰がどう決めるべきなのか。そして、私たちはどんな情報環境に身を置いているのか。ともに考える入り口として、まずは現状を見つめてみましょう。
規制強化の背景にある世界的潮流

「表現の自由」が揺らぎはじめたきっかけは、米国から
政治コンテンツに対する規制の流れは、ある意味、アメリカの混乱から始まったと言っていいかもしれません。2016年の米大統領選で、ロシアによるSNSを使った「世論操作」や「偽情報の拡散」が大きな問題となりました。結果、Facebook(現Meta)やYouTube、Twitter(現X)などのプラットフォームは「政治的コンテンツへの対応を強化せよ」という国際的な圧力に直面します。
選挙のたびに問題視されるのが、フェイクニュースがいかに短時間で大量拡散されてしまうかという点です。誰でも簡単に情報発信できるネット空間において、その“便利さ”が、いつしか“危うさ”へと裏返った。これに対し、プラットフォーム側は「過剰な検閲ではない、でも放置もしない」という、極めて難しい対応を求められるようになりました。
広告主の声が強める「ブランドセーフティ」重視の姿勢
もうひとつ、規制の流れを後押ししているのが、広告主側からの圧力です。企業は当然ながら、自社のブランドイメージを守ることを最優先に考えます。もしも、過激な政治的発言や誤情報の流れる動画の横に自社広告が出てしまったら、それはブランドにとって致命的です。
この考え方を「ブランドセーフティ」と呼びます。GoogleやMetaといった大手プラットフォームは、広告主からの信頼を維持するために、「危険なコンテンツには広告をつけない」という方針を強めてきました。政治に関わる話題はどうしてもセンシティブになりやすいため、「無難に避ける」判断がなされやすいのです。
収益化ポリシーの曖昧さと、広がる“自動制裁”
Googleが導入している収益化ポリシーは、「政治的にセンシティブな内容には広告を制限する場合がある」としていますが、その基準は必ずしも明確ではありません。実際、何の警告もなしに「収益化オフ」が適用されるケースも多く、発信者側は原因がわからず困惑することもしばしば。
さらに問題なのは、その判定がAIやアルゴリズムによって“自動”で行われているという点です。例えば、ある動画で「選挙」「政権」「戦争」といったキーワードが含まれているだけで、自動的に広告が外されてしまうこともある。これは“削除”よりもずっと静かで、しかし確実にダメージを与える「無言の制裁」だと言えます。
今は「削除」ではなく「見せない」時代へ
以前は、不適切とされる情報に対しては「削除」するのが基本的な対応でした。しかし近年では、「完全に消す」よりも「目立たせない」「収益をつけない」といった“抑制的”な手法が中心になりつつあります。これが、今まさに進行している「規制の新段階」です。
例えば、YouTubeのアルゴリズムは、広告がつかない動画をおすすめ欄に表示しづらくする傾向があります。つまり、収益化が外れるだけで、その動画は検索にも引っかかりにくくなり、視聴数が激減する。これは実質的には「発信力の剥奪」とも言えるのです。
こうした流れのなかで、政治や選挙について自由に発信するという行為そのものが、収益や拡散力の面でリスクを抱えるようになっています。そして、そのリスクの基準は“見えにくい”まま。これが、現代の政治的言論空間における最大の課題かもしれません。
フィルターバブルとエコーチェンバー

情報は「自分向け」に最適化されている
私たちは、毎日スマホを開き、SNSやYouTubeで情報を見ています。政治に関心があれば、自然と選挙の話題や政党の動き、評論家の意見などが目に入る。でも、ふと立ち止まって考えてみてください。その情報、本当に「多様」なものでしょうか?
実は、私たちがネット上で触れている情報の多くは、アルゴリズムによって“選ばれたもの”です。これまでの検索履歴、フォローしている人、視聴時間、クリックの傾向…こういったデータから「この人はこういう情報が好きだろう」と判断され、どんどん似たような投稿や動画が表示される仕組みになっています。
フィルターバブル:見えない“情報の泡”に閉じ込められる
このような状況がもたらす現象を、「フィルターバブル(Filter Bubble)」と呼びます。つまり、自分が興味のある情報や、自分と同じ考えの人の投稿ばかりが表示される“泡”の中に閉じ込められてしまうのです。
たとえば、ある政党を支持している人のフィードには、その政党を好意的に扱う情報ばかりが流れてきます。逆に批判的な意見や、他の立場の情報はほとんど目に入りません。気づかないうちに、私たちは「見たい世界」だけに囲まれているのです。
エコーチェンバー:同じ意見のこだまが響きあう空間
さらにこの状態が続くと、「エコーチェンバー(Echo Chamber)」、つまり“こだまの部屋”のような現象が起こります。同じような考えの人たちが集まって、お互いの意見を強化しあい、異なる立場を持つ人を排除していく。やがて「自分たちの意見こそ正しい」という確信が強まり、反対意見には耳を貸さなくなってしまうのです。
これは、民主主義にとって非常に危うい状態です。意見の多様性こそが、社会にとって健全な議論を生む土壌になるはずなのに、アルゴリズムがそれを“最適化”の名のもとに狭めてしまっているのです。
過激な意見が強化される構造
問題なのは、こうした情報の偏りが、発信者自身にも影響を与えているということ。たとえば、ある特定の政治的立場で動画を出すと再生数が伸びる、フォロワーが増える、収益も入る。となれば、「もっと尖った主張をしよう」「対立軸をはっきりさせよう」という方向に流れていくのは自然な流れです。
結果として、極端な意見や感情的な言い回しがネット上に増えていき、それを支持する“泡”の中でさらに強化されていく。この循環こそが、情報環境の分断を深める大きな要因です。
「収益化オフ」は偏りへのブレーキか、それとも…
ここで、前章の「収益化オフ」の話が関わってきます。プラットフォーム側が「政治的にセンシティブだ」と判断して収益を止めるというのは、過激化を抑えるための一手とも言えるかもしれません。けれど、それがあまりに広範囲かつ一方的に適用されると、逆に“穏やかで冷静な議論”までもが埋もれてしまう危険性があります。
見たい情報だけでなく、必要な情報に出会う工夫を
つまり私たちは今、「見たい情報だけを見る」「見せたい情報だけを見せる」環境の中で、情報の多様性や中立性をどう守るかという問いに直面しています。
技術が進化して、何でも検索できる時代になったけれど、その裏側で私たちの視野は意外と狭くなっているかもしれません。だからこそ、発信者だけでなく、私たち一人ひとりが「自分の情報環境」に敏感になることが求められています。
自分とは異なる意見にも耳を傾けること、アルゴリズムに任せきりにせず、あえて検索して新しい情報に触れてみること。それが、健全なネット社会をつくる第一歩かもしれません。
表現の自由と収益の自由、その線引きを誰が決めるのか

「表現してもいいけど、お金にはならない」は自由なのか?
政治的な意見をネットで発信すること自体は、法律で禁じられているわけではありません。憲法にも「表現の自由」はしっかり保障されています。しかし近年、プラットフォーム側の判断で「収益化をオフにする」=広告をつけさせない、という対応が増えてきています。
これ、実はかなり深刻な話です。発信者にとって広告収入は、活動の継続そのものに直結します。特に、政治や社会問題をテーマにした情報発信は、調査や取材、編集に時間がかかるうえ、内容によっては炎上や批判のリスクも伴います。そうしたリスクを負ってでも伝える意義があると思ってやっているのに、「収益はゼロです」と言われたら、多くの人は継続を断念せざるを得ません。
つまり、これは単に「広告がつかないだけ」ではなく、“実質的な表現の抑圧”とも言えるのです。
民間企業が“言論のライン”を引く時代
こうした判断を下しているのは、あくまで民間企業であるGoogleやMetaなどのプラットフォームです。国家の検閲ではありません。ですが、今や私たちの言論空間の多くがそのプラットフォーム上に存在している以上、そこにルールがあるというだけで、事実上の“表現の審査者”になっているという現実があります。
たとえば「選挙」「政党」「移民」「戦争」といったキーワードを含むコンテンツが収益化オフの対象になりやすいことは知られていますが、その適用は機械的でブラックボックス化しています。「どの表現がダメだったのか?」「何を直せば広告がつくのか?」が分からないまま、発信者だけが消耗していく。
この不透明さこそが、いま最も大きな問題かもしれません。
「自由に発信してもいいけど、誰も見ないし稼げないよ」では意味がない
もうひとつ考えておきたいのが、“表現の自由”と“届く自由”と“稼げる自由”はセットだということです。どれか一つでも欠ければ、その表現は社会的に無力化されてしまいます。
YouTubeでは、広告がつかない動画は「おすすめ」に載りにくくなる傾向があります。つまり、再生回数も自然と伸びなくなる。「削除」はされていないけれど、誰にも届かない。そんな“見えない規制”が、現実にはどんどん広がっているのです。
これは単に「お金の問題」ではありません。情報が可視化されるかどうか=社会に影響を与えられるかどうかという、もっと大きな力の話でもあります。
どこまでが「健全な制御」で、どこからが「不当な抑圧」なのか?
もちろん、何でもかんでも「自由にさせろ」というのも現実的ではありません。暴力的な扇動、差別的な発言、フェイクニュースの拡散…こういった内容が野放しになれば、社会の安全や信頼性が揺らいでしまいます。
だからこそ、一定の制御や判断は必要。でも、問題はそのルールが誰によって、どんな基準で、どのように運用されるかです。
現状では、ルールの設計も運用もプラットフォームの“内部事情”に委ねられているケースが多く、ユーザー側が納得できる説明や透明性はほとんど確保されていません。これは、言論の土台が民間企業の裁量に大きく依存しているという、非常に不安定な状態を示しています。
市民・発信者・プラットフォーム、それぞれに責任がある
最終的には、発信者・視聴者・プラットフォーム、それぞれに責任があります。発信者には、事実確認や冷静な言葉選びが求められるし、受け手にも情報を見極めるリテラシーが必要。そして、プラットフォームには、透明性あるルールと、公平な運用、そして説明責任が求められます。
ネットは自由な空間だからこそ、その自由をどう守るか、誰が線を引くべきかを社会全体で考えていく時期に来ているのではないでしょうか。
SNS・YouTube・ブログ:発信の手段とリスク

発信の「場所」が未来を左右する時代
インターネットが普及して以降、情報を発信する手段は爆発的に増えました。今ではYouTube、X(旧Twitter)、Instagram、TikTok、そしてブログやウェブサイトと、手段は無数にあります。特に政治や社会問題のような、議論を呼ぶテーマについても、誰もが手軽に発信できるようになったのは大きな進化です。
でも同時に、「どこで発信するか」は、ただの好みでは済まされないほど、内容の届き方・制限のされ方・リスクの持ち方が異なってきています。
【YouTube】リーチ力と収益性の裏にある“不安定さ”
まずは動画発信の代表格、YouTube。ここは今や個人がジャーナリズム的役割を担う場でもあります。映像の力は大きく、編集で説得力も増し、再生回数次第では広告収入も期待できます。政治YouTuberや選挙ウォッチャーが増えているのも納得です。
ただ、その裏には大きなリスクもあります。先に触れたように、広告のつき方が不安定で、突然の「収益化オフ」により生活が成り立たなくなることも。さらに、アルゴリズムの変更で急に再生数が伸びなくなる…なんてことも珍しくありません。
しかも、広告が外れるだけでなく、「関連動画」や「おすすめ」に載りづらくなるため、視聴者の目にも触れにくくなる。これは発信者にとって非常に大きなダメージです。
【X(旧Twitter)】即時性と拡散力、だが誤解や炎上の温床にも
X(旧Twitter)は、即時性と拡散力に優れた発信ツールです。ちょっとした発言が数時間で全国に広がることもあり、政治家も記者も一般市民も、リアルタイムで情報を発信・交換しています。
でも、文字数制限によって発言が短文化し、文脈の誤解や極端な意見の切り取りが起きやすいのも事実です。対話よりも“論破”が重視されやすく、炎上も頻発。アルゴリズムの仕様により、センセーショナルな内容ほど拡散されやすい傾向もあり、落ち着いた議論の場にはなりづらいという側面もあります。
【ブログ・ウェブサイト】自由度は高いが「孤立」との戦い
一方、個人ブログや自前のウェブサイトでの発信は、ある意味で最も自由度の高い方法です。外部のアルゴリズムや収益化ポリシーに左右されず、自分のペースで情報を発信し、表現のスタイルも自由自在。収益化の手段も、広告、寄付、サブスク、物販など多様です。
ただし、読者にどうやってたどり着いてもらうかが最大の課題。SNSでの拡散や検索エンジン最適化(SEO)を意識しないと、せっかく書いた内容が誰にも届かないまま終わってしまうことも。自分だけの発信拠点を持つことは重要ですが、それを「見てもらう工夫」も不可欠です。
ハイブリッド型が主流に? 組み合わせて発信の安定性を高める
現在、多くの発信者は複数のメディアを組み合わせて発信しています。たとえば、YouTubeで動画を出しつつ、その補足や裏話をXで展開し、さらに詳しい資料や全文解説をブログで掲載する、という具合です。
こうすることで、一つのプラットフォームに依存しない強さが生まれます。万が一、どこかが凍結されたり、収益が止まったりしても、他の手段でカバーできる。これは発信者にとって、いまや必須のリスクマネジメントと言えるでしょう。
表現の「自由」は、選べる環境があってこそ成り立つ
ネット上での発信は、場所によって見え方も届き方も変わります。だからこそ、自分が何を伝えたいのか、どのように届けたいのかによって、発信の手段を選ぶことが重要です。
同時に、プラットフォーム側には「選択肢を狭めない努力」、受け手には「どんな手段で発信された情報なのかを見極める力」が求められています。自由な言論空間を守るためには、ツールを使いこなす知恵と、それを支える多様なインフラが必要なのです。
利用者の責任とリテラシー:情報の受け手としての自律

情報は「受け取る側」にも責任がある
ネット上には、毎日膨大な情報が流れています。その中には、政治や選挙に関する有益な情報もあれば、誤解を生む表現、意図的に偏った主張、あるいはフェイクニュースも混ざっています。これだけ多様な情報が飛び交う今、重要なのは「どれを信じ、どう判断するか」です。
発信者にばかり「正確さ」や「公平性」を求める声もありますが、それと同じくらい大切なのが、私たち受け手の“リテラシー”です。情報に接するときの態度や心構え、それ自体が社会全体の情報環境を形作っているのです。
“わかりやすさ”だけを求めると、危うくなる
現代は「わかりやすい情報」が好まれる時代です。要点だけを切り取ったまとめ動画、短い文章で済むSNS投稿、図解やランキングで整理されたコンテンツ。もちろん、それ自体は悪いことではありません。時間がない中で要点を掴めるのは便利ですし、興味の入口にもなります。
しかし、「わかりやすさ」が行きすぎると、複雑な現実を単純化しすぎてしまうこともあります。「○○党は悪」「○○候補は正義」といった、白か黒かで語る情報は、見ていて気持ちがいいかもしれません。でも、現実の社会や政治は、そんな単純な構図では説明できないものばかりです。
だからこそ、受け手には「これって本当に正しいのかな?」「反対の意見も見てみよう」という一歩引いた姿勢が求められます。
「自分の考えと違う意見」にどう向き合うか
SNSやYouTubeでは、自分の意見と似た情報ばかりが表示される傾向があります。前に触れたフィルターバブルやエコーチェンバーの影響ですね。そうすると、だんだんと「反対意見は間違っている」と思い込みやすくなってしまいます。
でも実は、「違う考えに触れること」は、リテラシーを育てる最高のトレーニングです。すぐに賛成する必要はありません。むしろ、「なぜこの人はそう考えるのか?」と背景や立場を想像する力が、情報社会においてとても大切なのです。
意見が違う人に出会ったとき、「ブロック」や「ミュート」で避けてしまうのは簡単です。でも、それを繰り返していくと、自分の考えがどんどん固定化されて、他者との対話の糸口が失われていきます。
アルゴリズム任せにしない“能動的な情報収集”を
今や、私たちが目にする情報の多くは、プラットフォームのアルゴリズムによって選ばれています。でも、本当に大事な情報が、必ずしも「おすすめ」に出てくるとは限りません。
だからこそ、「自分で探しに行く姿勢」が重要になります。検索を工夫する、公式サイトで一次情報を確認する、立場の異なるメディアを見比べてみる。ほんの少しの手間が、情報の正確さや広がりを大きく変えてくれるのです。
「待っていれば流れてくる情報」だけでなく、「自分で取りに行く情報」にも目を向けてみましょう。
「見抜く力」から「育てる力」へ
そしてもうひとつ大切なのが、「批判する力」だけでなく「育てる力」を持つこと。発信者の表現を「粗探し」するだけでなく、伝え方が未熟な情報に対しても「こうしたらもっとよくなるかも」と思えるような視点があれば、情報環境そのものが豊かになります。
ネットは誰もが主役になれる時代です。だからこそ、一人ひとりが情報空間の“参加者”であり、社会の情報環境を支える存在だという自覚が求められています。
ネット時代の政治とメディア:新しい合意形成の可能性

政治が“日常会話”になるチャンス
かつて政治といえば、「専門家や新聞記者が語るもの」「テレビで見るもの」というイメージが強かったかもしれません。でも今は違います。YouTubeやSNSを通じて、政治や政策について自分の言葉で語る人が増え、ネット上のいたるところで“政治の話題”が飛び交うようになりました。
これは、とても大きな変化です。政治が「誰か遠い人の話」ではなく、「自分たちの暮らしとつながっているもの」として語られるようになったのは、ネット時代ならではの価値ある流れです。
そして今後、この流れをどう“熟議”につなげていくかが、私たちの社会にとって大きな鍵になるでしょう。
多様な立場が出会い、議論する場をどうつくるか
とはいえ、ネット上の政治的言論は、対話というより「主張のぶつけ合い」になってしまうことも少なくありません。お互いの立場を理解しようとせず、敵味方で線を引いてしまうと、議論は深まらず、分断だけが残ります。
そこで大切なのが、「立場の違う人と、どう対話するか」を意識した環境づくりです。コメント欄でのマナーや、異論を歓迎する雰囲気づくり、さらには「その人がなぜそう考えるのか」に耳を傾ける姿勢が求められます。
政治は一つの正解を見つけるものではなく、多様な価値観のあいだで“折り合い”を探していくプロセスです。だからこそ、「違う考えの人と話す」ことを恐れず、むしろ歓迎する空気を、ネット上でも育てていく必要があります。
メディアの役割も問われている
政治や社会の問題をどう伝えるか。これは発信者や市民だけでなく、既存メディアにとっても重要な課題です。ネットで情報が自由に流れる時代になった今、新聞やテレビも「情報の供給者」から、「信頼の仲介者」へと役割が変わりつつあります。
ネット上では、スピードと話題性ばかりが優先されがちですが、そこにメディアが「検証」や「背景説明」といった付加価値を与えることで、議論の質を引き上げることができます。
また、メディアがオンライン空間での対話の場を主催する、あるいは市民の声をすくい上げる仕組みをつくるなど、“合意形成の土台”となる役割を担っていくことも期待されます。
ネットの発信が「政治参加の入口」になる
一つ忘れてはならないのは、ネットでの発信や対話が、現実の政治参加へとつながる可能性を持っているということです。候補者の比較、政策の読み解き、地元の課題の可視化…そういった情報が共有されることで、「投票」や「意見提出」といった具体的なアクションへと人々を後押しします。
たとえば、ある市民が自分の地域の問題をSNSで発信したことがきっかけで、議会での議論が始まったという例もあります。こうした「個人の発信が政治を動かす」事例がもっと広がっていけば、政治と市民の距離はさらに縮まるはずです。
“分断”ではなく、“対話”と“合意”を積み上げる時代へ
政治的な意見が対立するのは、ある意味で当然のことです。価値観も立場も、誰ひとり同じではありません。でも大事なのは、「違う意見だから分かり合えない」と諦めるのではなく、「どうすれば一緒に社会をつくっていけるか」を考えることです。
ネット空間には、対話を深めるための可能性がまだまだ眠っています。いがみ合うのではなく、共に考え、共に築く場所としてのネット。そこを目指すことが、これからの社会には必要なのではないでしょうか。
政治発信の未来と、わたしたちの選択

政治を語ることは、特別なことじゃない
政治という言葉には、どこか“堅い”“面倒くさい”“対立のもと”というイメージがつきまといます。でも実際のところ、政治とは「私たちの暮らしにどんなルールを適用するか」「社会をどう運営していくか」を決める仕組みのこと。つまり、私たち一人ひとりの日常と切っても切り離せないものです。
だから、政治について語ることは、本来とても自然なことであり、特別な専門知識が必要なわけでもありません。感じたこと、疑問に思ったことを発信する。それだけで十分な「参加」です。
表現と収益、その間に横たわるジレンマ
本コラムでは、政治コンテンツに対する「収益化オフ」の動きから始まり、フィルターバブルやエコーチェンバー、表現と収益の境界、発信手段の違い、そして情報リテラシーまでを見てきました。
特に重要なのは、「表現する自由」と「それで食べていく自由」のあいだに、見えないけれど確実な“線引き”が存在しているという現実です。発信者は自分の主張を伝えるために時間と労力を費やし、視聴者に届けようとします。その活動が「収益化オフ」によって封じられるとしたら、それは表現の自由を“静かに抑圧する”結果になりかねません。
技術と社会が進化したからこそ、私たち自身の判断が問われる
AI、アルゴリズム、プラットフォーム…現代の情報環境は、あらゆる技術に支えられています。でも、技術がどれだけ進んでも、最終的に「何を信じて、どう行動するか」を決めるのは人間自身です。
発信する側は、事実と意見のバランスに配慮しつつ、冷静で誠実な言葉を紡ぐことが求められます。そして受け手である私たちは、その情報を鵜呑みにせず、自分の頭で考え、他者の視点にも触れる努力が必要です。
技術が情報を「届ける力」をくれる一方で、正しく受け止める力は、人間にしか持てないのです。
「関心を持つこと」からすべては始まる
政治の話をする、選挙について語る、社会課題に意見を持つ。それだけで「発信者」としての第一歩を踏み出したことになります。何万人に届かなくてもいい。たとえ一人でも、誰かの考えるきっかけになれば、それは立派な社会参加です。
ネット時代の今だからこそ、その小さな声がつながり、波紋を広げ、社会を少しずつ動かしていくこともあります。発信の形は無限大。動画でも、文章でも、画像でも、会話でも。どれもが価値ある一歩です。
私たちの選択が、言論空間の未来をつくる
政治を語る自由、それを支える経済的仕組み、そして多様な声が出会い合意をつくる場。どれも、他人任せにできるものではありません。今この瞬間も、誰かがルールを決め、誰かが線を引いている。それを見て見ぬふりをするのか、主体的に関わっていくのか。その選択が、これからのネット社会の姿を左右します。
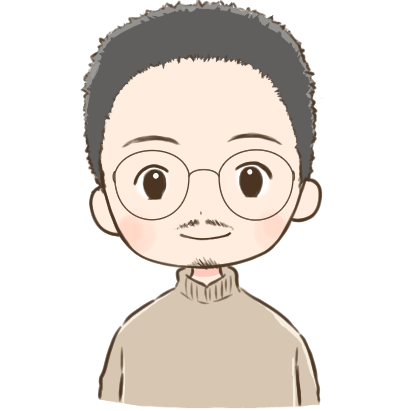
語ることをやめない。考えることをやめない。そして、自分の声の力を信じる。
それこそが、政治発信の未来にとって最も重要な「選択」なのではないでしょうか。
このブログを読んでのご感想など
このブログ記事を読んでのご感想をお送りください。ブログを書く励みになったり、もしかすると読者からのメッセージとして記事で紹介させていただくこともあるかもしれません。お気軽にどうぞ。