2025年5月16日

豊橋新アリーナ建設計画について住民投票実施へ
豊橋市で長年議論されてきた「新アリーナ建設計画」をめぐり、ついに住民投票が実施される運びとなりました。これは市政における大きな転換点であり、単なる施設建設の是非を問うにとどまらず、市民参加のあり方や政治家の姿勢が問われる機会でもあります。
この住民投票は突然現れたものではありません。市民団体や有志の住民たちは、2020年代の初頭から継続的に住民投票の実施を求めて運動を展開してきました。チラシの配布や署名活動、議会への請願提出、街頭での呼びかけなど、あらゆる方法で「市民に判断を委ねるべきだ」という声を届けようとしてきたのです。
しかし、当時の浅井由崇市長はこの要望に対して極めて消極的な姿勢を取りました。市側は「十分に説明してきた」「必要な手続きは踏んでいる」として、住民投票の必要性を否定。説明会の開催やパンフレット配布などをもって「市民理解は進んでいる」とする姿勢を崩しませんでした。こうした行政の態度は、市民の多くに「市政が私たちの声を本気で受け止めていない」という失望感を生む結果となりました。
さらに問題なのは、市議会の対応でした。特に自民党市議団は、住民投票を求める陳情や請願に対し、ほぼ一貫して「否決」という態度を取り続けました。「我々議員が市民の代表なのだから、市民の代弁者として議会が判断すればよい」という論理が繰り返され、結果的に市民の直接的な意思表示の機会は閉ざされ続けたのです。
このときの姿勢を振り返れば、現在の動きには大きな「変節」があることが否応なく浮かび上がります。なぜ今になって、議会が住民投票の実施に前向きになったのか。その背後には、市民世論の高まりや政局的な計算、あるいは次の選挙を意識した対応といった複数の要因が複雑に絡み合っている可能性があります。
今回の住民投票の実現は、確かに前進ではありますが、それは「市民の声に耳を傾け始めた」という前向きな変化であると同時に、過去の無視の積み重ねへの帳尻合わせでもあるのです。市民が真摯に訴えていたときには動かず、行政の都合や外的圧力によってようやく態度を変える。そのような受動的な変化に対して、私たちは素直に喜んでよいのか、慎重に見極める必要があるでしょう。
豊橋の未来を市民の手で選ぶ機会がようやく訪れた今、私たちは改めて問わなければなりません。「なぜこれまで市民の声は届かなかったのか」「なぜ今、突然聞く耳を持ち始めたのか」その理由と背景を忘れてはならないのです。

浅井市長時代の「市民の声」の軽視
豊橋新アリーナ計画が市民の関心を集める中、前市長・浅井由崇氏が在任していた時期の対応は、果たして本当に「開かれた市政」と言えるものであったのでしょうか。住民投票の実施を求める声が繰り返し上がる中で、浅井市長が示してきたのは、一貫して「住民投票は必要ない」という強硬な姿勢でした。表向きには「丁寧な説明を行っている」「十分な情報公開をしている」とされていましたが、その実態は市民の真意に寄り添うものとは言いがたいものでした。
実際、当時市民からは次のような声が粘り強くあがっていました。
浅井市長時代の「市民の声」
- 「この事業の財政負担は本当に持続可能なのか?将来的な維持費はどうなるのか?」
- 「人口が減り続けている中で、本当に新たな大型施設が必要なのか?」
- 「既存の施設では本当に代替できないのか?リニューアルという選択肢は検討されているのか?」
こうした疑問や提案は、単なる反対のための反対ではなく、冷静で現実的な観点からのものでした。市民の多くが「ゼロベースで考え直してほしい」と訴えていたのです。また浅井市長も市長選に立候補したときには「ゼロベースで見直す」ことを公約にしていました。しかし、当時の市政はそれらの声に対して、実質的に議論を封じるような対応を続けていました。
その典型が「説明会開催」の一言で済ませてしまう姿勢です。確かに市主催の説明会は行われました。しかし、その内容は一方的に計画の必要性や経済効果を訴えるものであり、疑問に対してきちんと答える場ではありませんでした。参加者からの厳しい質問が出ても、それに対して曖昧な回答に終始するケースが目立ちました。
さらに、説明会で使用された資料やパネルも「都合のいいデータ」に偏っていたという指摘があります。例えば、経済波及効果の数値は出ているものの、長期的な維持管理費や赤字リスクについての試算は十分に示されていませんでした。また、他都市のアリーナ事業の失敗例など、懸念材料に関してはほとんど触れられませんでした。
市側の対応には「聞いているふり」の印象が強く、形式的には意見を受け付けるが、実質的には計画ありきで進んでいるという感覚を多くの市民が抱いていました。結果的に、「説明はされたが、納得はしていない」という声が市内各所で聞かれるようになり、行政と市民の間に目に見えない温度差が生じていたのです。
「市民参加」という言葉が語られながらも、その実態は表層的なアリバイ作りにとどまり、市民との対話や合意形成という民主主義の根幹を軽視する姿勢が続いた…これが前政権における最大の問題だったと言えるでしょう。
なぜ今になって「住民投票容認」なのか?

今回、豊橋市議会の一部を占める自民党市議団が、これまでの姿勢を転換し、住民投票条例案に賛成の意を示したことは、大きな変化として注目されました。これまで頑なに住民投票を拒んできた立場から一転、「市民の声を真摯に受け止めた結果」と説明しています。けれども、現場の市民感覚としては、素直にこの前向きな変化を歓迎することができない、ある種の引っかかりを抱いている人も多いのではないでしょうか。
というのも、この方針転換には多くの疑問が残るからです。
自民党市議団の方針転換への疑問
- なぜ、浅井市政時代に同じく住民投票を求める声が上がっていたにもかかわらず、その時には真っ向から否定していたのか?
- なぜ、あれほど頑なだった立場を、今になって突然「住民の意思を確認すべきだ」と180度変えるのか?
- 政策の一貫性はどこにあるのか?かつての否決行動について、市民に対して説明や謝罪はあるのか?
こうした疑問に対して、明確な説明はなされていません。表面上は「市民の声が大きくなったから」「情報が行き渡ったから」といった理由が語られますが、それは裏を返せば、これまでの自らの説明や対応が不十分だったと認めることに他なりません。
背景には、市民世論の高まりや次回選挙を見据えた戦略的判断があることは想像に難くありません。住民投票の請願署名は短期間で1万筆以上を集め、市民の間での関心は一気に高まりました。SNSやメディア報道も追い風となり、これまでのように「議会が判断すればいい」という理屈では通用しなくなってきたのです。
議員たちは、こうした世論の空気を無視すれば自らの政治的立場が危うくなると判断し、「住民投票に賛成することで市民の理解を得よう」という動きに転じた可能性があります。つまり、市民の声を聞いたというより、聞いたふりをすることでポジションを確保したようにも見えるのです。
このような態度の変化は、私たち市民にとって、単なる「柔軟な姿勢の転換」ではなく、「都合よく変わる価値観の危うさ」を感じさせます。もしこれが、政治的リスクを回避するための方便だったとすれば、「市民の声を聞く」とは一体何なのか、根本から問い直さなければなりません。
政治において判断が変わることは、時として必要なことでもあります。しかしそれは、過去の判断をどう総括し、どのように市民に説明し、信頼を取り戻していくのかというプロセスを経てこそ、正当な変化といえるはずです。唐突に態度を変えて、説明もないまま「市民のため」だとだけ言われても、市民が納得できるはずがありません。
私たちが求めているのは、結果としての賛成ではなく、誠実な姿勢の変化です。今後もこうした「都合の良い変化」が繰り返されるようでは、市政に対する信頼は根底から崩れてしまうでしょう。
地元の課題には無関心・市民に寄り添っていない現実
私は自治会長時代、毎朝の登校見守り活動や通学路の安全確保に尽力してきました。特に幹線道路を避けるように設定された通学路に、渋滞回避の抜け道として多くの車が流入し、子どもたちの命が常に危険にさらされている現状を、肌で感じてきました。
その中でもとりわけ危険なのが、住宅街の中央線も歩道もない狭い道路を猛スピードで走り抜ける車両の存在です。路側帯すら車に占有され、子どもたちは車道を歩かざるを得ず、すぐそばを車がすれ違っていく。そんな状況を、何年も前から市議会議員に伝えてきました。
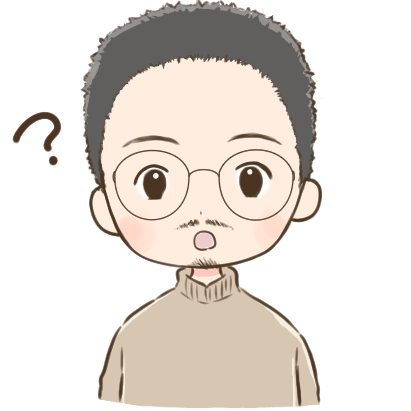
この通学路をスクールゾーンにしてもらえませんか?
一度現場を見ていただけませんか?
そうお願いしても、市議から返ってきたのは「反対する人もいる」「署名活動しないと無理ですね」といった言葉。現地を確認する様子もなく、まるで取り合う気がない。確かに法的な手続きや合意形成は重要ですが、なぜ命に関わる通学路の安全対策だけが、こんなにも軽視されるのか。
それなのに、豊橋新アリーナのような大型公共事業となると、「市民の声を聞いて進めるべきだ」と急に前のめりになる。沿線住民の反対があっても、高速道路やアリーナ計画は強引に推し進める。なぜ、わずか300メートルのスクールゾーン化には「反対があるから」と後ろ向きになるのか。この対応の差に、私は強い疑問を抱かずにはいられません。
地域に根差し、市民の命を守るのが政治の本分であるはずです。目立つ案件には熱心でも、子どもたちの命を守る地道な課題には背を向ける。これが本当に「私たちの代表」の姿なのでしょうか。
都合よく使われる市民の声

ここまでの流れを見ていると、政治家が掲げる「市民の声を大切に」という言葉が、どれほど空虚なものになってしまっているのかが、徐々に浮き彫りになってきます。とりわけ、豊橋新アリーナのような注目度の高い大型プロジェクトにおいて、「住民の意思が重要だ」「市民の理解を得て進めたい」といった表現が頻繁に使われる一方で、地域の身近な課題、たとえば通学路の安全対策や生活道路の整備、子どもや高齢者の見守りといった日々の生活に直結する問題に対しては、驚くほど鈍感で無関心であるという現実があります。
つまり、「市民の声」とは、彼らにとって使えるときだけ使う政治的資源にすぎないのではないか?そう疑わざるを得ません。都合のいい場面では「市民の意思を尊重するべきだ」と前面に押し出しながら、不都合な要望や扱いづらい問題には「慎重に検討する必要がある」「反対意見もある」などと言って先送りにする。このような姿勢を目の当たりにしている市民の多くが、政治家の言う「市民参加」に対して疑念を抱くのも無理はありません。
私自身、自治会長として多くの住民の声を預かってきました。その中には、先に述べたような「通学路の抜け道問題」といった、まさに命と安全に関わる切実な声が含まれていました。しかし、それらの声が政治の場で本気で取り扱われた記憶は残念ながらほとんどありません。むしろ、「署名活動が必要」「反対意見もある」などとかわされるだけで、実質的には棚上げにされてきました。
一方、アリーナや高速道路、インフラ整備といった見栄えのいい事業では、何かあれば「市民が望んでいる」「地域経済の活性化につながる」という形で、市民の名前が持ち出されます。まるで、政策を正当化するための免罪符として「市民の声」を使っているようにしか見えないのです。
しかし、「市民の声を聞く」というのは、本来そうした都合の良い道具ではなく、政治の原点そのものであるべきです。どれだけ小さな声でも、それが市民の生活や命に関わるものであれば、真っ先に耳を傾け、向き合うのが代表者としてのあるべき姿のはずです。政治家がその役割を忘れ、数と派閥と世論操作ばかりを重視するようになれば、民主主義は形骸化し、市民の信頼は確実に失われていくでしょう。
「市民の声」は、都合よく使い分けるものではなく、常に対話の起点として、政策判断の核心に据えるべきものです。注目を浴びるプロジェクトだけではなく、日々の生活に根ざした声にこそ誠実に応える。その姿勢を持ってこそ、政治と市民の信頼関係は築かれていくのではないでしょうか。
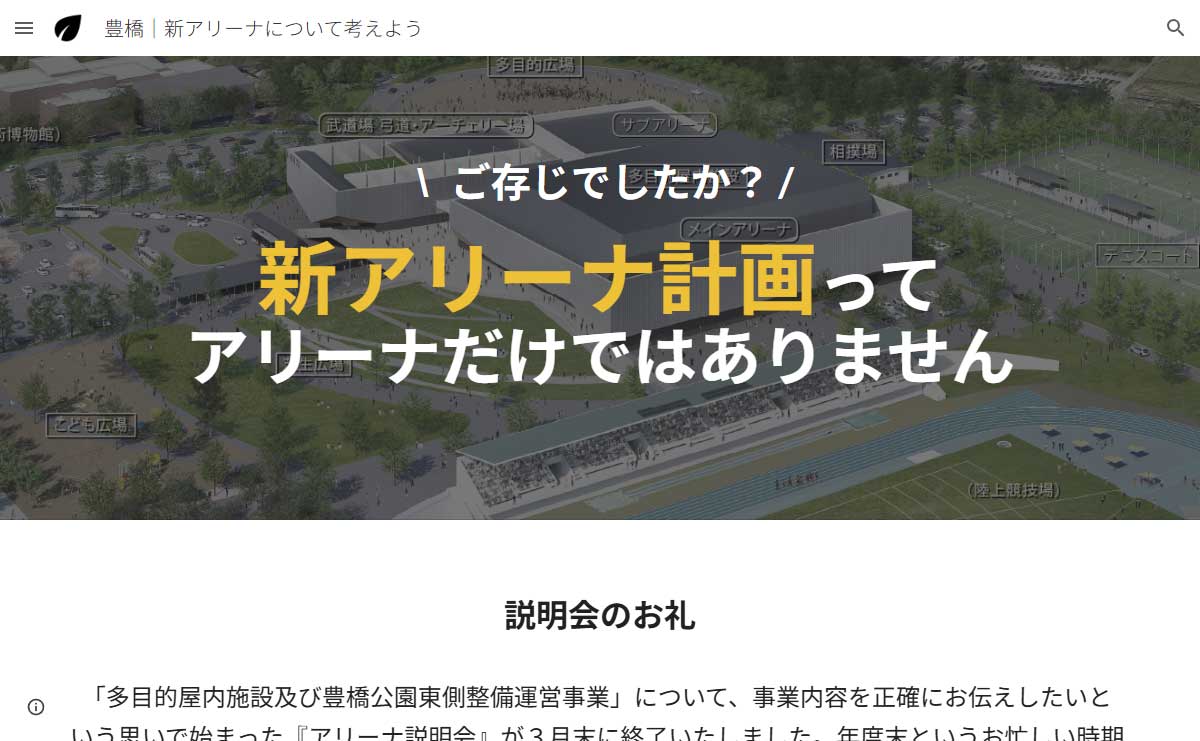
住民投票はアリーナだけでなく「豊橋市政のあり方」を問う
今回、豊橋市で実施される住民投票は、新アリーナの建設計画そのものについて是非を問う場です。しかし、私たちがこの機会に本当に見つめ直すべきは、「これまで政治家たちが市民の声をどう扱ってきたか」という、市政運営の根本的な姿勢です。
かつて住民投票を求める声が無視され続けた事実、そしてその姿勢が今になって突然変化した理由…この「変節」に対して、政治家たちは説明責任を果たしたでしょうか?市民の声が政策の正当化に使われるだけで、都合が悪くなると無視されるようなあり方を放置していては、また同じことが繰り返されてしまいます。
この住民投票は、ただ「建設に賛成か反対か」を示すだけのものではありません。私たち市民一人ひとりが、政治家の姿勢と誠実さ、そして市政の進め方そのものに対して意思を示す機会でもあるのです。
「市民の声をどう扱うのか」「説明責任をどこまで果たすのか」この住民投票を通して、政治のあり方そのものを問い直す。私たちには、その権利と責任があります。

このブログを読んでのご感想など
このブログ記事を読んでのご感想をお送りください。ブログを書く励みになったり、もしかすると読者からのメッセージとして記事で紹介させていただくこともあるかもしれません。お気軽にどうぞ。
