2025年9月11日

令和の「米騒動」
ここ最近の米の価格高騰には驚かされます。スーパーに並ぶ値札を見て「えっ、こんなに上がったの?」とつぶやく方も多いのではないでしょうか。ニュースやネット上では、これを「令和の米騒動」と呼ぶ声すら聞かれるほどです。
米は日本人の食卓に欠かせない主食だからこそ、その値上がりは家計に直結し、不安や不満を呼び起こします。ある程度の年齢以上の人にとっては、自然と平成の「米騒動」を思い出すのではないでしょうか。あの1993年、冷夏による深刻な不作で米不足となり、タイ米などの輸入米がスーパーに並んだ出来事です。慣れない香りや味に戸惑いながらも、何とか食卓をしのいだ経験は今でも記憶に残っています。
あの時は「米が無い」という物理的な不足が騒動の中心でしたが、今回は価格の高騰が生活を直撃しています。性質は違えど、米をめぐる混乱が時代ごとに繰り返されているのは興味深いものです。そして話はここで終わりません。「令和」や「平成」だけではなく、実は「昭和」にも「米騒動」があったのをご存じでしょうか。食糧問題ではなく、大学入試、共通一次試験の数学の問題がきっかけで起きた騒動だったのです。
昭和の米騒動とは?
「米騒動」と聞くと食糧不足を想像する人が多いでしょう。しかし昭和の「米騒動」は少し毛色が違います。昭和60年(1985年)に行われた共通一次試験の数学で起きた出来事です。
共通一次試験の解答用紙はマークシートです。0から9までの数字と*(アスタリスク)が並んでいてそれぞれに塗りつぶすマークがあります。例えば問題の解答が「25」だった場合一つ目は2のマークを塗りつぶし、二つ目に5のマークを塗りつぶします。
で、数学のマークシートは解答が2桁の場合は2つ分のマークが3桁の場合は3つ分のマークがあるので問題を解く前から解答は2桁とか3桁とか想像できてしまいます。では*(アスタリスク)は何に使うのかというと、解答に3つのマークする欄があった時、計算したら2桁の解答だった場合に使います。
例えば解答欄に3つのマークする欄があった時に解答が「25」だった時一つ目は2のマークを塗りつぶし、二つ目は5のマークを塗りつぶします。そして三つ目のマークの「*(アスタリスク)」を塗りつぶすのです。
この昭和60年の共通一次はぼくは実は2度目の共通一次。つまりは一浪したわけですが前の年の共通一次はもちろん、過去問、様々な模擬試験などでも*(アスタリスク)を使った記憶なんてありません。それが問題の最初の方の簡単な計算問題から*(アスタリスク)が必要な答えが出ました。
正直、最初は簡単な計算ミスと思いましたが、何度計算しても*(アスタリスク)が必要です。戸惑いながらも問題を進めていくと次から次へと*(アスタリスク)を必要とする解答が出てきます。ぼくは数学は得意科目で模擬試験などでも数学はほぼ満点です。国語と社会が目も当てられない点数なので数学でしっかり稼がないといけません。

めっちゃ焦りました!
結局終わってみれば十数個の*(アスタリスク)を使いました。数学の試験は割と余裕で終わるのが常でしたがこの時は試験時間ギリギリまで何度も見直し計算しなおしました。
この非常に疲れた試験時間が終わってトイレに行ったり廊下で息抜きしたりする人みんな何となく重苦しい雰囲気です。ぼくは仲の良い友達に…
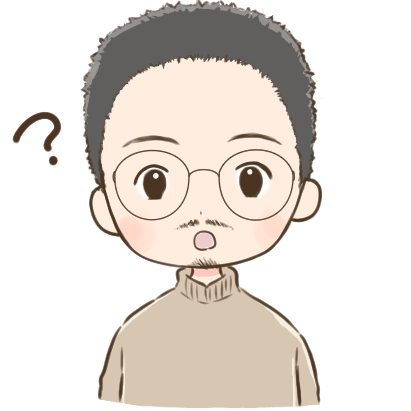
なぁ…米印使ったか?
と聞きました。

おぉ、めっちゃ使った!
そしてあちこちから「コメ使ったか?」「コメすごかった」「こんなコメはじめてだわ」
とザワザワし出しました。幸いぼくは数学が得意であったのと何度も見直したので自己採点では190点以上でしたが友人の中には*(アスタリスク)に惑わされて大きく点を落とした人もいました。
この珍事はすぐに「米騒動」と呼ばれて話題となり、新聞や雑誌でも取り上げられました。食卓の米不足ではなく、数学の問題文に出てきた「米」が日本中の受験生を騒がせたのです。今でも昭和60年に受験した人しか知らない受験体験談の笑い話として語り継がれています。
受験生あるあるの共感ネタ
受験という特別な舞台に立つと、普段ならなんでもないことが大きな壁に見えてしまうものです。昭和の「米騒動」もその典型例でした。本来なら単なるマークシートの仕組みに過ぎないアスタリスクが、試験本番という極度の緊張と重なって受験生の心をかき乱しました。
「模試では一度もこんな場面はなかったのに…」という不安が、普段の実力をあっさり覆い隠してしまうのです。これは受験生なら誰もが経験したことがある「あるある」ではないでしょうか。普段の勉強では解けるのに、試験会場では時計の針の音や隣の鉛筆の走る音に気を取られ、簡単な問題で計算ミスをしてしまう。あるいは、見慣れない記号や言い回しに出くわした瞬間、頭が真っ白になる。
冷静に考えれば大したことはないのに、本番の空気が平常心を奪っていくのです。さらに「模試では満点近かったのに本番では点が取れなかった」という悔しさも、多くの人の胸に残っているはずです。受験は実力勝負であると同時に、メンタルや環境への適応力を試される場でもあります。昭和の米騒動は、そんな受験生の心理を凝縮したエピソードとして昭和60年の共通一次を受験した人の心に残っています。
「米騒動」と日本人の米への縁
日本人にとって米は、単なる主食を超えた特別な存在です。平成の米不足を経験した世代なら、スーパーに長蛇の列ができ、見慣れないタイ米を手にした記憶を持つでしょう。食卓に並んだその独特の香りに戸惑いながらも「これもまた仕方ない」と受け入れたあの夏。あれはまさに生活を直撃する「米騒動」でした。
ところが昭和の米騒動は食卓ではなく試験会場で起きたのです。共通一次のマークシートに登場した「米印(*)」が受験生を混乱させ、学力ではなく心の動揺を試した事件となりました。冷静に見れば単なる記号に過ぎませんが、受験という人生の岐路に立つ場面で出会った「米」は、多くの受験生の心をざわつかせました。
こうして考えると、米は食べ物としてだけでなく、日本人の人生の節目に不思議な形で関わってきた存在だと言えます。腹を満たすだけでなく、時に受験の勝敗を分け、社会全体を揺さぶる。米という二文字には、我々の生活や心情を左右する力が宿っているのかもしれません。だからこそ令和の米価格高騰もまた、単なる物価問題を超えた「大事件」として語られるのではないでしょうか。米はやはり、日本人にとって切っても切れない縁を持つ存在なのかもしれません。
まとめ~令和の米騒動に寄せて
令和の米価格高騰を前に、私たちは再び「米騒動」という言葉を口にしています。平成の米不足では、実際に食卓から米が消え、タイ米に慣れないながらもしのいだ経験がありました。そして昭和の米騒動では、試験問題の「米印(*)」が受験生の心を揺さぶり、大きな混乱を生みました。
いずれも本質は異なるものの、「米」という存在が人々の日常を大きく動かした点では共通しています。米は食べれば腹を満たし、無ければ不安を生み、記号になれば受験生を惑わせる。まさに日本人の人生のあらゆる場面で、波乱を巻き起こす不思議な力を持っていると言えるでしょう。今回の令和の騒動も、単なる物価上昇にとどまらず、私たちが「米との関わり」を改めて見つめ直すきっかけなのかもしれません。
昭和・平成・令和と、時代ごとに形を変えて登場する「米騒動」。そのたびに人々が右往左往し、ときに笑い話として記憶に残すあたりに、日本人のしたたかさとユーモアが見えてきます。最後に言えるのは、「やっぱり米は日本人にとって特別な存在」ということ。令和の米騒動も、いずれ時を経て「あの頃は大変だったね」と語り継がれる、また一つの思い出になるのでしょう。
このブログを読んでのご感想など
このブログ記事を読んでのご感想をお送りください。ブログを書く励みになったり、もしかすると読者からのメッセージとして記事で紹介させていただくこともあるかもしれません。お気軽にどうぞ。