2025年7月8日


はじめに:今朝の新聞記事を読んで思ったこと
今朝の中日新聞(東三河版)に、豊橋新アリーナ計画をめぐる住民投票に関して、賛成・反対両派の市民団体代表のインタビュー記事が掲載されていました。残念ながら、新聞購読をしていないとWebでは全文を読むことができませんが、もし機会があれば、ぜひコンビニや図書館、喫茶店などで手に取ってみてください。豊橋市に住む者にとって、今まさに直面している大きなテーマについて、賛成派、反対派の声が丁寧に取り上げられている内容です。
さて、今日のこのインタビュー記事を読んで、今更ながらに僕はある点に気づかされました。それは推進派の代表として登場している人物が、行政ではなくプロバスケットボールチーム・三遠ネオフェニックスの支援企業の方であるということです。これまでの豊橋新アリーナ建設推進の説明会などでもこの方がよく前面に出てきています。
行政ではなく「支援企業」側の人物が前面に出ている違和感
今回の中日新聞の記事では、新アリーナ計画をめぐる賛成派の立場として「新アリーナを求める会Neo」代表の小林佳雄さんが登場しています。これまでにも新アリーナ推進の説明会や意見交換の場などでたびたび前面に出ていた方なので、目にしたことのある市民も多いのではないでしょうか。
ただ、改めて冷静に考えてみると、ここに一つ大きな違和感があります。それは、賛成派の顔として登場するのが、行政の代表者ではなく、プロバスケットボールチーム・三遠ネオフェニックスの支援企業の方だという点です。
一方で、反対派の藤田茂樹さんは「豊橋公園の緑を未来につなぐ市民の会」の共同代表として、計画に対する懸念や問題点を、市民としての目線から丁寧に語っておられます。藤田さんの発言には、納税者であり、将来にわたってまちに住み続ける者としてのリアリティがあります。市の財政負担への危惧、手続きの不透明さ、防災上の課題など、どれも「生活者」としての実感に根差した意見です。

それに対して、小林さんの発言は「イノベーション」や「地域アイデンティティ」、「目に見えるハードへの投資」といった、企業経営者としての感覚やまちづくり理念に近いものでした。それ自体を否定するものではありませんし、地域に情熱を注ぐ存在であることも確かです。ただし、それはあくまで「市の事業を応援する立場」であり、事業主体としての責任や説明義務を負っているわけではありません。
市民が本当に知りたいのは、「なぜこの場所に建設するのか」「なぜこれほどの予算規模なのか」「将来的な維持費はどうなるのか」といった、行政が責任を持って答えるべき部分です。しかし、その問いに正面から向き合うべき行政の姿が、ここには見えてきません。
豊橋新アリーナ建設は、230億円以上の公費が関わる巨大プロジェクトです。そしてその資金の出どころは、他ならぬ市民の税金です。であるならば、本来ならばこの住民投票の局面において、計画を推進したいのであれば、行政が正面に立ち、説明を尽くすのが筋ではないでしょうか。
市民にとっては「事業主体である市の見解を、行政自身の口から聞きたい」というのが自然な感情です。民間の熱意に頼る構図が続くことで、かえって「市はなぜ出てこないのか?」「本当は説明責任を果たしたくないのではないか?」といった疑念が生まれてしまいます。
言い換えれば、今回のコラムの出発点となった違和感は、行政不在のまま民間の支援者が計画の「代弁者」として振る舞っているという構図に対して、市民感覚が「それはおかしい」と感じている証でもあるのです。
市長が「見直し」を公約に掲げて当選した事実
今回の豊橋新アリーナ計画をめぐる議論において、忘れてはならないのが、現在の長坂市長が2024年の市長選挙で「アリーナ計画の見直し」を公約に掲げて当選したという事実です。この背景には、当時から多くの市民の間に計画そのものや進め方への疑問、不信感が根強く存在していたことがあります。前市政が主導してきた方針を一度立ち止まって考え直すべきだ、という市民の意思が選挙というかたちで表れたとも言えるでしょう。
その一方で、住民投票が近づく中、推進派の側として前面に立っているのは市ではなく、三遠ネオフェニックスの支援企業の方です。「豊橋新アリーナを求める会Neo」の代表として市民の前に立ち、アリーナ建設の意義を語る姿勢は目立ちますが、行政の側から計画を推進する積極的な説明は表立って見えてきません。この点に、少なからず違和感を覚える市民もいるのではないでしょうか。
もっとも、長坂市長の立場にも一定の理解は必要だと思います。市長は「見直し」を掲げて当選している立場であり、自らが計画について語れば、どうしてもこれまでのアリーナ計画の問題点に触れざるを得ません。その結果、反対の立場と受け取られるおそれがあるため、市長として中立的に住民投票に向けた発信を行うことには難しさがあるのも事実です。
実際、市長は2025年7月にオンライン形式で説明会を開催しており、その内容は現在もYouTubeで公開されています。そこで市長は、自身の立場や豊橋新アリーナ計画を取り巻く背景、見直しの経緯などについて丁寧に説明しています。こうした情報発信の努力は評価すべき点だと思います。
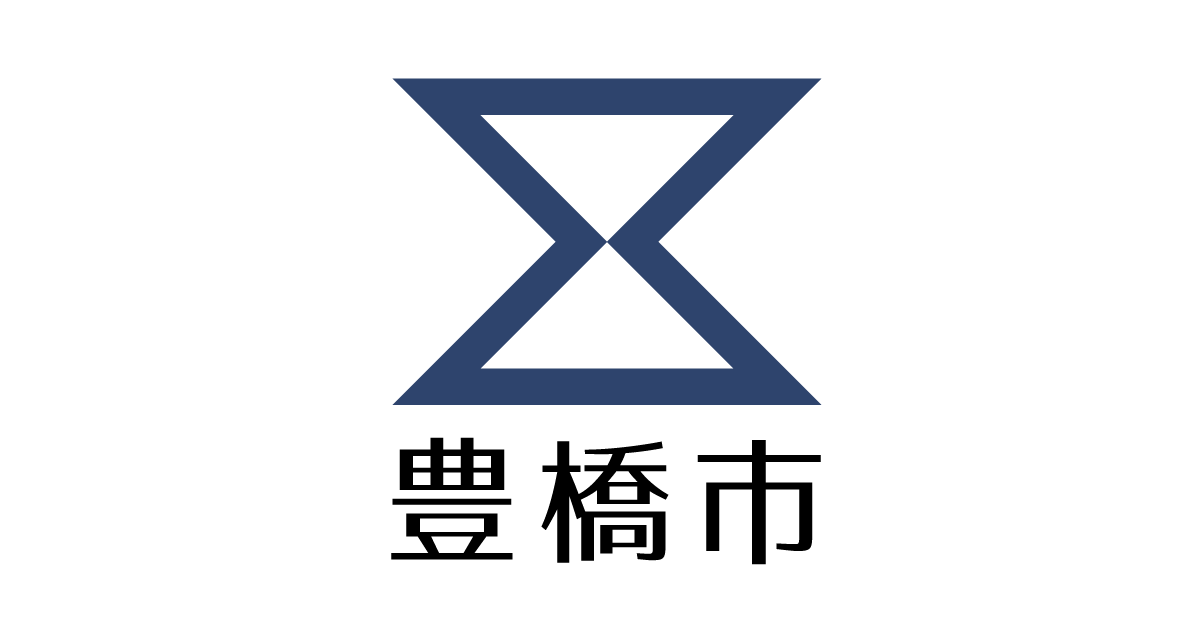
とはいえ、住民投票を目前に控えた今、より広い層に届くかたちでの説明が必要なのではないかと感じます。市長自身が発言を控えるならば、代わりに行政の担当部門が計画の意図や現在の状況、今後の選択肢について中立的かつ具体的に市民に示す場を、もう少し積極的に設けるべきではないでしょうか。
住民投票は市民が未来を選ぶ重要な手段です。その判断が一部の熱心な支援者の声やムードに左右されてしまわないよう、行政が果たすべき「冷静で公正な情報提供」という役割は、今こそ改めて問われているように思います。
行政の沈黙を補う「支援者」の発信は正当なのか
「豊橋新アリーナを求める会Neo」の代表である小林佳雄氏は、これまでも一貫して豊橋新アリーナ建設の必要性や意義について、積極的に発信を続けてこられました。今朝の中日新聞のインタビューでも、まちの誇りや地域アイデンティティ、若者への投資といった前向きな視点から、熱意ある主張を展開されていました。その情熱や地域に対する思いは、確かに尊重されるべきものだと思います。
しかしながら、小林氏の語る言葉がいかに魅力的であったとしても、それが即、市民全体の納得につながるわけではありません。なぜなら、豊橋新アリーナ建設にまつわる論点には、「公共施設としての役割」「公金の投入規模」「将来の改修費」「防災拠点としての適格性」など、制度的かつ具体的な行政課題が数多く含まれているからです。
これらは、単なる「夢」や「希望」だけでは語れない領域です。費用の妥当性、事業手法の透明性、他の公共事業との優先順位など、こうした点を市民に正確に伝え、理解を得ることは、本来は行政の責任です。ところが現実には、その説明を十分に果たしているのは行政ではなく、支援者の立場にある民間の人物なのです。
もちろん、小林氏の発信そのものを否定するつもりはありません。むしろ、豊橋というまちをより良くしたいという思いがあっての活動であることは、多くの市民も感じ取っていることでしょう。しかし、だからといって、市の事業を推進する役割までを民間人が一手に担っているような構図が続くことには、やはり違和感が拭えません。
重要なのは、行政が自らの責任で、公共性の観点から事業の全体像とその意味を市民に説明することです。その上で、支援者や市民団体がそれぞれの立場から意見を述べるという順序が、本来の筋なのではないでしょうか。
市民の多くは、「この計画が良いか悪いか」以前に、「ちゃんと説明されていない」「納得できるだけの情報がない」というところで立ち止まっているように見えます。行政が沈黙を続けることで、民間人の声だけが先行している現状は、そのバランスを欠いていると言わざるを得ません。
誰がこの事業の責任を負うのか」が曖昧なまま進んでいないか?
豊橋新アリーナの建設計画は、総事業費が230億円を超える巨大な公共プロジェクトです。これだけの規模であれば、本来ならば行政が前面に立ち、市民に対して事業の目的、根拠、将来の見通し、そして費用の妥当性について、責任を持って説明すべきです。
しかし、現状を見ていると、その「説明の主役」が行政ではないように見えてしまいます。住民投票を前にして、最も前面で推進の意義を語っているのは、行政でも市長でもなく、プロスポーツチームを支援する企業の方です。もちろん、その方に思いや意志があることは否定しませんが、そもそも市の事業を語る場面で、なぜ行政ではなく民間の人物が代表的な存在になっているのでしょうか。
仮に、このまま住民投票で「推進」が多数を占めたとしても、それが本当に「民意を得た」と言えるのかどうかには、疑問が残ります。市民が必要な情報を十分に得たうえでの判断でなければ、票の結果が「納得」や「合意」につながらない可能性があるからです。
さらに、計画の見直しを公約に掲げて当選した現市長が、この住民投票のタイミングで前に出ず、説明を避ける姿勢を取っていることも、問題を複雑にしています。結果として、かつての計画を推進してきた前市政の方針を、今は市民でも行政でもない企業人が代弁しているような構図になっており、行政としての責任の所在が非常に曖昧です。
これは、市民から見れば「誰がこの事業の責任を本当に負っているのか」がわからない状況です。そしてその不明瞭さこそが、多くの市民が計画に対してモヤモヤとした不信感を拭えない原因のひとつではないでしょうか。
説明責任を果たさないまま、結果だけを受け取ろうとする行政の姿勢は、まさに「責任を負わない説明」と言わざるを得ません。これでは、住民投票が民主的なプロセスであっても、その正当性や信頼性に対して市民の納得が得られにくくなるのではないかと感じます。
市民に問われているのは「施設の善し悪し」ではなく「市政のあり方」
豊橋新アリーナの建設計画については、その規模やデザイン、スポーツ利用と文化イベントとの両立、さらには防災拠点としての機能まで、実に多岐にわたる論点が存在しています。それぞれに重要なテーマであり、市民にとって身近で関心の高い問題であることは間違いありません。
しかし、今回の住民投票で市民に本当に問われているのは、そうした施設の仕様や設計の善し悪しだけではありません。本質的には、「このまちの大きな意思決定が、どのような手続きで、誰によって進められてきたのか」という、市政そのもののあり方が問われているのだと思います。
行政の説明が足りていないと感じる市民がいる一方で、民間企業の支援者が顔となって語っている現状。市民が見ているのは、個々の機能性やデザインではなく、「誰が声を上げ、誰がそれに応えているのか」という構図です。公共事業において、住民の理解と納得を得るプロセスが十分だったのかどうか。それこそが、今あらためて問われているのではないでしょうか。
主役は市民であるべき
アリーナ建設のような大規模な公共事業においては、その事業を担う行政こそが、まず率先して説明責任を果たすべき存在です。市民からの疑問や懸念に対して、丁寧に、そして誠実に向き合うことが、行政としての基本的な姿勢だと思います。
支援企業や市民団体の熱意は決して否定されるべきものではありません。むしろ地域への強い想いから出てきた行動であることに違いはありません。しかし、だからといって、その声だけに依拠し、行政が前面に出てこないという構図が続くことは、本来の順序を欠いていると言えるでしょう。
市が果たすべき役割は、熱意を煽ることではなく、冷静に事実と数字を示し、全体像を市民と共有することです。計画に関わるリスクや費用、市の将来像への影響について、判断材料となる情報を正確に、わかりやすく提示する。そのうえで、住民が自らの意思で投票という行動を選択できる環境を整えることこそが、行政の責任です。
住民投票は、賛成か反対かという単純な二択ではありません。それは市民が市政と向き合い、信頼関係を築き直す貴重な機会です。その場に肝心の行政が姿を見せないという事実こそが、今回の議論における最大の違和感であり、私たちがこれからも問い続けるべき課題ではないでしょうか。
このブログを読んでのご感想など
このブログ記事を読んでのご感想をお送りください。ブログを書く励みになったり、もしかすると読者からのメッセージとして記事で紹介させていただくこともあるかもしれません。お気軽にどうぞ。
