2025年3月28日

2025年3月、選挙ポスターの掲示ルールに制限を設ける改正公職選挙法が成立しました。この改正は、街中に無制限に貼られていたポスターが景観を損ねたり、トラブルの原因になったりしていたことを背景にしています。しかし、今回の法改正では触れられていない大きな課題が残されています。それが、SNS上で広がる「偽情報」への対策です。
今や、選挙においてSNSは欠かせない情報発信ツールとなっています。候補者が政策や人柄を直接伝えられるメリットがある一方で、根拠のない噂や悪意あるデマが一気に広まり、有権者の判断を狂わせるリスクも高まっています。特に選挙期間中は、誤った情報が拡散されれば選挙結果にまで影響を与えかねません。
こうした状況を受けて、与野党からは「SNS上の偽情報対策を急ぐべきだ」との声が相次いでいます。ただし、対策の内容によっては「選挙活動の自由」や「表現の自由」を制限するおそれもあるため、慎重な議論が求められています。SNS上の偽情報問題と、選挙における自由な発言とのバランスについて、各政党の考えや今後の課題をもとに考えてみましょう。
なぜSNS上の偽情報が問題なのか
SNSは今や、選挙情報を得るための主要な手段の一つとなりました。候補者自身が政策や活動をリアルタイムで発信でき、有権者との距離も縮まりました。しかしその反面、大きな問題となっているのが「偽情報」の存在です。
SNS上では、誰でも自由に情報を発信できます。その利便性の裏側で、根拠のない噂話や事実と異なる内容、さらには意図的な誹謗中傷などが一気に拡散されることがあります。これらの偽情報は、テレビや新聞と違って事前のチェックがされないため、瞬く間に多くの人に届き、真実のように受け止められてしまうことがあります。
特に選挙期間中は、有権者が限られた時間の中で情報を判断し、投票する相手を決めることになります。そこに偽情報が入り込めば、有権者の判断を誤らせ、結果的に選挙の公正性が損なわれる恐れがあります。選挙とは民主主義の根幹です。その信頼性を揺るがす要因として、SNS上の偽情報は非常に深刻な課題なのです。
実際、国内でも過去の選挙で「○○候補が逮捕された」といった虚偽の情報が拡散され、後にデマだと判明する事例がありました。国外ではアメリカの大統領選やイギリスのEU離脱(ブレグジット)などにおいて、偽情報がネット上に大量に流れ、世論に影響を与えたと指摘されています。
こうした事例からもわかるように、SNSが政治に与える影響は年々大きくなっており、単なるネット上の「うわさ話」では済まされない段階に来ています。だからこそ、偽情報への対策を急ぎつつ、どうすれば正当な情報発信の自由を守れるかが問われているのです。

各政党の考え方は?
SNS上の偽情報対策については、各政党とも問題意識を共有しつつも、そのアプローチには違いがあります。それぞれの主張を見ていくことで、課題の複雑さと今後の議論の方向性が浮かび上がります。
まず、自民党の逢沢一郎・選挙制度調査会長は「インターネットがデマや中傷の拡散に使われる状況にあり、公正な選挙が保たれるようにする必要がある」と述べ、SNSの適正な利用のあり方を訴えました。選挙制度の信頼性と民主主義の維持を重視し、一定のルール整備が必要だという立場です。
一方、立憲民主党の重徳和彦政調会長は「選挙活動の自由度をどこまで制約できるのか」と慎重な姿勢を見せつつも、当選目的ではない形での立候補、いわゆる「2馬力立候補(※一方が票を割ることで他方の当選を助ける行為)」については規制の必要性に言及しました。自由な選挙活動を守りながら、悪質な行為には歯止めをかけたいという立場です。
国民民主党の川合孝典・参院幹事長は、「SNS発信で収益を得られないようにする縛りが大事」と主張しています。これは、SNSを利用して選挙関連の投稿で広告収入を得たり、フェイクニュースによって利益を得る構造を断ち切ることを意図しています。資金的なインセンティブが偽情報拡散の一因になっていると見ているわけです。
公明党の岡本三成政調会長は「表現の自由を守りつつ、必要な法整備があれば対応する」と述べ、憲法上の自由とのバランスを強調しました。規制一辺倒ではなく、自由な言論空間の維持を意識した慎重な対応を求めています。
この4党以外の政党でも、SNSの影響力を踏まえた議論が進められています。たとえば、日本維新の会は以前から政治とネットの関係に積極的で、情報の透明性を高める方向での改革を重視しています。一方で、共産党などはネット空間での監視強化が表現の自由を脅かす危険性について警鐘を鳴らしています。
つまり、どの政党も「偽情報への対策は必要」としながらも、その方法については「選挙の自由」「表現の自由」「経済的背景」「公正性」など、さまざまな観点から立場が分かれています。今後の法整備には、これらの視点を丁寧にすり合わせる作業が不可欠でしょう。
各政党の主張
- 自民党(逢沢一郎氏)
- デマや中傷の拡散を懸念
- 公正な選挙と民主主義を守るためにSNSの適正利用が必要
- 一定のルール整備を主張
- 立憲民主党(重徳和彦氏)
- 選挙活動の自由を制限しすぎないよう慎重姿勢
- 「2馬力立候補」など悪質行為への対策は必要と指摘
- 国民民主党(川合孝典氏)
- SNS発信で収益を得られないようにする制限が重要
- 偽情報拡散の金銭的インセンティブを断つことを重視
- 公明党(岡本三成氏)
- 表現の自由を尊重
- 必要に応じて法整備に対応する姿勢
- 日本維新の会
- 政治とネットの関係に積極的
- 情報の透明性を高める改革を重視
- 共産党
- 過度な監視が表現の自由を脅かすと懸念
- 言論の萎縮を警戒
課題と今後のポイント
SNS上の偽情報対策を進めるにあたって、いくつもの重要な課題が存在しています。中でも特に焦点となるのが「選挙活動の自由」「表現の自由」とのバランスです。どこまでが健全な言論で、どこからが規制すべき偽情報なのか。その線引きは非常に難しく、慎重な検討が必要です。
偽情報対策と選挙活動の自由のバランス
候補者にとって、SNSは政策を伝え、有権者との距離を縮める大切なツールです。その活動を規制しすぎれば、かえって民主主義を損なう恐れもあります。しかし放置すれば、根拠のないデマや誹謗中傷が氾濫し、有権者の正確な判断が妨げられることになります。選挙活動の自由を守りつつ、悪意ある情報操作には厳しく対応する。そのバランスをどう取るかが、最大の課題といえるでしょう。
表現の自由の範囲と線引き
日本国憲法では「表現の自由」が保障されています。これは政治的発言にも当然含まれ、選挙期間中であっても自由な発言の場を保証する必要があります。ただし、虚偽情報や悪意のある操作が「表現の自由」の範囲に含まれるべきかどうかは別問題です。特にAIやボットを使った偽情報の自動拡散など、技術的に高度な手口が増える中で、どのような発信を制限するか、その基準づくりが求められています。
民間SNS企業の対応と協力のあり方
偽情報対策を国が進めるうえで、SNSを運営する企業との連携は不可欠です。たとえばFacebook(現Meta)やX(旧Twitter)、YouTubeなど、選挙情報が拡散される主要プラットフォームには、投稿の監視や削除、アカウントの一時停止などの措置を取る体制が必要です。しかし、企業側にすべてを委ねると、恣意的な言論制限につながる可能性もあります。透明性と説明責任を確保した形での、官民連携が重要になります。
海外の事例から学べることは?
海外ではすでに偽情報対策が進んでいる国もあります。たとえば、ドイツでは違法な投稿の削除を義務づけた「ネットワーク執行法(NetzDG)」が施行されており、一定時間内に対応しなかった企業に罰金を科す仕組みがあります。アメリカでは2020年大統領選をきっかけに、SNS企業が積極的に「事実確認ラベル」を表示するなどの取り組みを始めました。
日本でもこれらの事例を参考にしながら、独自の制度設計が求められます。ただし、文化的・法制度的な違いもあるため、単純に模倣するのではなく、日本の社会に合った形で調整する必要があります。今後は、法整備だけでなく、情報リテラシー教育の推進や、国民自身が情報を見極める力を高めることも、偽情報対策の一環として欠かせない視点になっていくでしょう。
「情報リテラシー」の向上が大切
SNSの普及により、私たちは選挙に関する情報を手軽に得られる時代になりました。しかしその一方で、根拠のない噂や悪意ある偽情報もまた、簡単に広まる時代になってしまったことを、私たちは重く受け止める必要があります。特に選挙のように、一票の重みが国の将来を左右する局面では、正確な情報が担保されなければなりません。
こうした状況を踏まえれば、SNS上の偽情報への対策はもはや避けて通れない課題です。ただし、だからといって過剰な規制によって、候補者の自由な発言や、有権者の多様な意見表明までが萎縮してしまうようでは本末転倒です。健全な民主主義には、自由な議論と開かれた表現の場が必要不可欠です。
だからこそ今、求められているのは、厳しすぎず緩すぎない「透明性のあるルールづくり」です。そしてそれと並行して、国民一人ひとりがネット上の情報を正しく見極める「情報リテラシー」の向上も重要です。法律と教育、制度と意識の両輪でこの課題に向き合っていくことが、これからの民主主義を守る道ではないでしょうか。
SNSには便利な情報もあれば、信頼できない情報もあります。あなたは、選挙のときにSNSで流れる情報を、どうやって見分けていますか?そして、表現の自由を守りながら、偽情報への対策を進めるには、どんな仕組みやルールが必要だと思いますか?
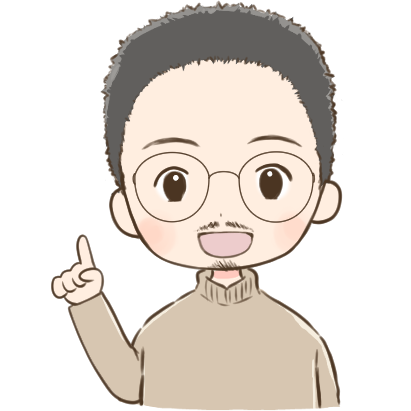
ぜひ一度、ご自身のSNSの使い方や、情報の受け取り方を振り返ってみてください。選挙は、私たち一人ひとりの意識から変わっていくものです。
このブログを読んでのご感想など
このブログ記事を読んでのご感想をお送りください。ブログを書く励みになったり、もしかすると読者からのメッセージとして記事で紹介させていただくこともあるかもしれません。お気軽にどうぞ。