2025年4月2日

この記事を読んでくれているということは、もしかして…あなたもこの新年度、新しく自治会長・町内会長になったばかりですか?もしくは、なりそうな予感にちょっと不安を感じている頃でしょうか。
その気持ち、痛いほどわかります。というのも、僕自身がまさに「えっ、オレ!?」という感じで、ある日突然、自治会長を引き受けることになった人間だからです。結局2022年度と2023年度の2年間自治会長を務めることになりましたが気苦労も多く大変だった半面、学ばせてもらった部分も多く今振り返れば引き受けてよかったと思うこともあります。
そんな僕の経験を交えながら今、自治会長や町内会長をやることになってしまったあなたへの多少なりともアドバイス、エールになればと思い、この記事を書いています。
まさかのご指名、そのとき僕は…
あれは2021年の年末のことでした。当時の自治会長と地域の「まちづくりの会」の会長が我が家に突然やってきて、
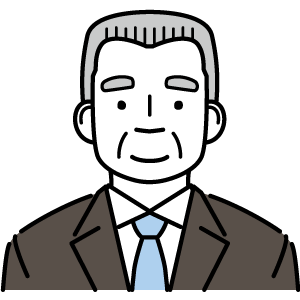
来年度、自治会長をお願いできないか?
と。僕の住む自治会は500世帯で40程度の組で構成されていて10組くらいで「ブロック」を構成していて自治会内には4つのブロックがあります。
自治会長はブロックの輪番でその年の自治会長は3ブロックの方でした。翌年度は4ブロックから自治会長を選ぶことが自治会の規約には書かれています。ぼくは翌年度「組長」をやる当番でしたが3ブロックですので自治会長をやらされることはないと思っていました。
しかし、
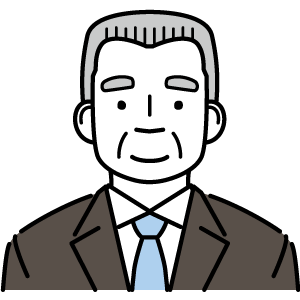
4ブロックの人が誰もやってくれない
と。それで面識もあり以前、小中学校でPTA会長をやっていたこともある僕に「自治会長もできるでしょ?」と安直な考えでお願いに来たようです。
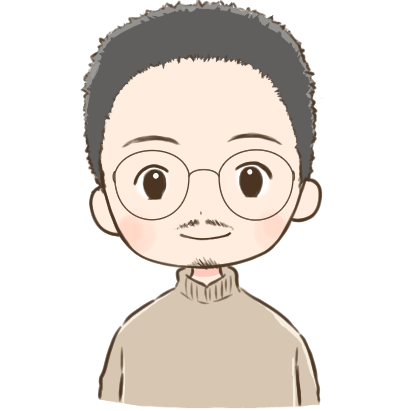
でも、それは違うでしょ?
僕は「ルールが違う」と断りましたが、二人は全然帰ろうとしてくれません。結局「頼むから!」と何度も頭を下げられ、断りきれずに引き受けることに…。
しかもタイミングが悪くて、新型コロナの影響で地域活動はほぼ停止中。引き継ぎも資料もほとんど無い。情報がゼロに近い状況からのスタートでした。でも、

誰かがやらなきゃ始まらないよな…
と思い、覚悟を決めたんです。
「自治会長の仕事」って…何をすればいいの?
正直、最初はわからないことだらけでした。「書類って誰が出すの?」「ゴミのことって自治会が関わるの?」「防災訓練ってどう進めるの?」…などなど、頭の中は「???」でいっぱい。でも、1つずつ確認したり、先輩たちに話を聞いたりしているうちに、徐々に流れが見えてきました。
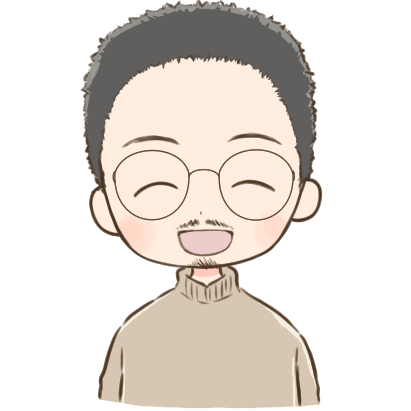
「全部ちゃんとやらなきゃ」と思いすぎると、気疲れします。目安は“7割でOK”。残りの3割は、次の代に残してもいいし、みんなで考えていけばいい。むしろ頑張りすぎる方が周囲のハードルを上げてしまうこともありますよ。
自治会長を乗り切るコツは「人に頼る力」
自治会長、町内会長といっても、元々は一住民です。ある日突然会長になったからと言って一人で何でもできるようになるわけないんです。
周りの人に頼ろう!
- 「助けて」が言える勇気を!
-
副会長さん、組長さん、前任者など、周りには意外と頼れる人がいます。遠慮せず、「これ、ちょっと教えてもらってもいいですか?」と声をかけてみてください。多くの人は快く応じてくれます。
- 丸投げしてもいい!
-
忙しい時は、「これ、お願いできますか?」と任せる勇気も必要です。何でも自分でやろうとすると、息切れします。チームでやる気持ちが大事。
あなたの生活が最優先です!
これは本当に声を大にして伝えたいんですが…自治会活動って、あくまで“ランティアなんです。決して「仕事」ではないし、義務でもありません。だからこそ、自分の体や生活を犠牲にしてまで頑張る必要はないんです。
ついつい「ちゃんとやらなきゃ」「みんなに迷惑かけたくない」と思って、無理をしてしまう気持ち、僕もそうでしたからよく分かります。でも、体調を崩したり、仕事や家族との時間に支障が出てしまっては、本末転倒ですよね。
たとえば…
- 会議資料を作ろうと思ってたけど、今日はクタクタ…。そんなときは、思い切って「明日やればいいや」と切り替えてOK。
- 行事や集まりがどうしても無理なときは、「誰か代わりにお願いできませんか?」と相談する勇気を持ってください。周囲は案外、快く助けてくれるものです。
- 「この行事、今年はやめようか」「今回はパスさせてもらおうかな」というやらない選択肢があってもいいんです。それは手抜きではなく、健全な判断です。
自治会って、地域のためにやるものだけど、その前にあなた自身が元気であることが一番大切です。無理をしてまで続けるのではなく、自分の暮らしやペースを大事にしながら、できる範囲で関われば十分なんです。
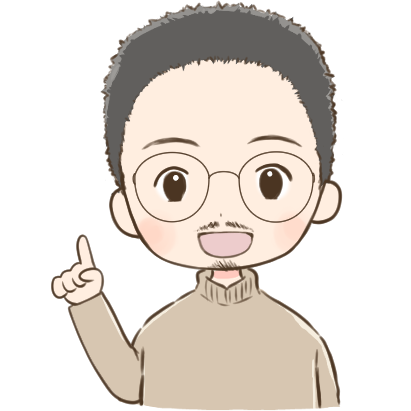
大丈夫。がんばりすぎなくても、地域はちゃんと回ります。あなたの小さな気遣いや笑顔ひとつで、きっと地域もやさしく変わっていきますよ。
前例に縛られない、あなたらしさでOK!
「毎年こうやってるから」「昔からこの方法なんだよね」―自治会に関わっていると、そんな言葉を耳にすることって結構ありますよね。もちろん、長年続いてきたやり方には、それなりの意味や背景があって、決して無視していいものではありません。伝統や地域の文化を大切にする姿勢はとても大事です。
僕はPTA会長をやっていた時にもずいぶんと「去年まではこうだった」と言われました。でも実際は多くのPTA役員さんも「それって必要?」って感じていることも多いんですよね。
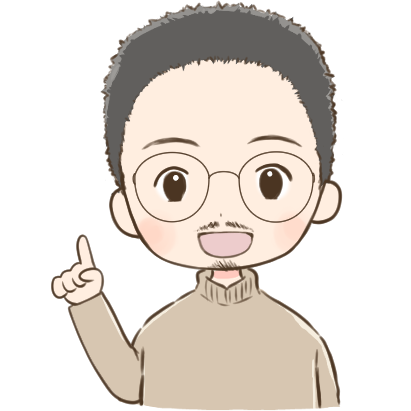
必要ないと思って無くした行事も必要ならまたやればいいじゃん。
伝統や地域の文化を大切にする姿勢はとても大事ですが、それと同じくらい大切なのが、今の時代に合ったやり方にアップデートする柔軟さだと思うんです。生活スタイルも、働き方も、家族のかたちも、10年前とは大きく変わっています。ましてや、今はデジタルも進化していて、ちょっとした工夫で手間や時間をぐっと減らせる場面も多いんですよね。
僕が自治会の新しい在り方のために取り組んでみたこと
- 回覧板で紙を回すのではなく、回覧内容をスマホで見られるようにQRコードを貼り出して共有する。これだけで、「読んだ・読んでない問題」や「回すの忘れた!」がかなり減ります。
- 会議の資料はGoogleドキュメントやOneDriveなどの共有ツールを使って、役員で同時に閲覧&編集できるように。わざわざ集まらなくても、それぞれが家で確認できます。
- 連絡は電話じゃなくてLINEグループやメールで簡単に。また、自治会や各団体用にはオープンチャットの活用もしました。スマホが使える世代にはとても便利な時代になりましたよね。
こういった工夫って、ちょっとしたことなんですが、やる側・受け取る側の両方がラクになります。そして何より、「便利になったね」「やりやすいね」と感じてもらえることで、地域の活動にも少し前向きに関わってもらえるようになります。
もちろんこのような方法を取り入れることで特に高齢者は不安に思うものです。いきなり変えてしまうのではなく少しずつ変えていき、これまでの方法も残すという柔軟な方法が住民に受け入れてもらえると思います。
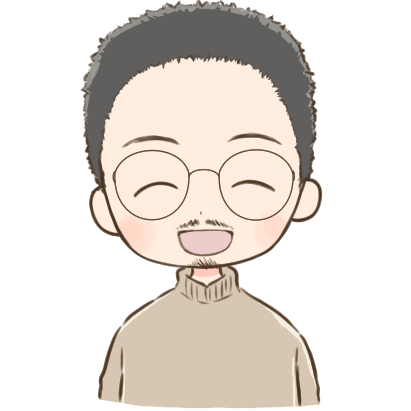
前例や慣習にとらわれず、「こうしたらもっとスムーズかも」「自分だったらこうしてほしいな」と思うことを、少しずつ試していけばいいんです。変えることを恐れずに、自分らしいやり方で自治会を育てていく。それも、あなたにしかできない大切な役割なんですよ。
スケジュールは「ざっくり把握」がカギ!
自治会長になったばかりの頃って、「何から手をつければいいんだろう…」と不安になりますよね。そんなとき、まず最初にやっておくとラクになるのが年間スケジュールのざっくり把握です。
新年度が始まったら、前年度の資料や引き継ぎ書類などを参考にして、どんな行事や会議、作業が1年のうちにあるのかを確認してみましょう。「この月は○○の清掃」「秋には防災訓練」「年末は資源回収の調整」など、ざっと全体像をつかむだけでも、心構えがずいぶん違ってきます。
スケジュールがわかったら、スマホのカレンダーアプリや紙の手帳にメモしておくのがおすすめです。通知機能を使えば、忘れそうな行事も事前に思い出せますし、「気づいたら明日だった!」なんてことも防げますよ。
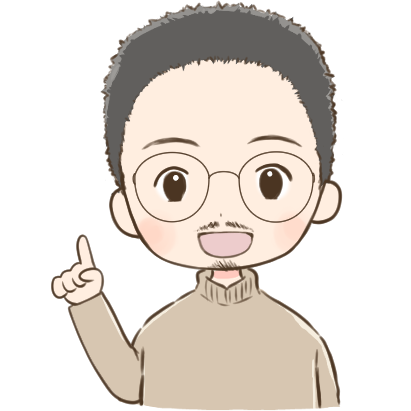
僕の場合コロナ後であったため様々な行事が中止されていました。前年度の情報が何もなく大変だった半面、長年続いてきたよくわからない行事の整理をすることができたのがよかったと感じています。
自治会の行事を見直してみよう!
- この行事、ホントに必要?
毎年やっているから…と続けているイベントでも、実は参加者がほとんどいなかったり、負担ばかり大きかったりするものもあります。思い切って見直すことで、みんなの負担がグッと軽くなるかもしれません。 - もっと簡単にできないかな?
行事の準備や当日の進行など、「ここを短縮できそう」「外注できないかな」など、ラクにできる方法を探してみましょう。効率化はサボりではなく、立派な工夫です。 - やめても困らないものは無い?
地域の実情に合わなくなったイベントや、目的がぼやけてしまった活動は、いっそのこと休止してみてもOK。すべてを続ける必要はありません。
会議は短く、分かりやすく!
自治会の会議って、ただでさえ平日の夜や休日に行うことが多いですよね。仕事終わりに駆けつけたり、家族との予定を調整して出席したり…。だからこそ、「短く・分かりやすく・サクッと終わる会議」が本当に大切だと感じています。
長時間ダラダラ続く会議ほど、参加者の集中力も切れてしまうし、肝心の決定事項がうやむやになりがち。「何の話してたっけ?」「結局どうなったの?」といったモヤモヤが残ってしまうことも珍しくありません。
会議をスッキリ進めるために
- 議題はできるだけ絞ること。
あれもこれも話したくなる気持ちはわかりますが、欲張ると逆にまとまりません。大事なテーマだけに絞って「今日はこれだけ決めよう」と明確にしておくと、参加者の意識も集中します。 - 時間は最大でも1時間以内。
時間が決まっていると、自然と話し合いのテンポも良くなります。「あと○分で終わるようにしましょう」と冒頭で伝えておくと、全体が引き締まります。僕は30分を目標にしていました。 - 資料はA4・1枚で十分。
会議用の資料は、つい作り込みたくなりますが、読む人にとってはシンプルな方がありがたいもの。要点だけを箇条書きにしてA4一枚にまとめるくらいが、いちばん親切です。
それだけで会議の空気がガラッと変わります。「またこのメンバーで集まりたい」「これなら参加してもいいな」と思えるような、心地よい場づくりができますよ。そしてなにより、時間を大切にしてくれる人には、自然と協力したくなるものです。参加者一人ひとりの貴重な時間を尊重すること。それが、信頼される自治会長の第一歩だと思います。
苦情・トラブルには、まず「傾聴」
自治会長をしていると、避けて通れないのが地域の方からのクレームや困りごとの相談です。「○○さんの車が邪魔で…」「あの家の騒音がひどいんだけど」「街灯が切れてて危ない」など、内容はさまざま。
最初は「自分が対応しなきゃいけないのか…」と焦ったり、「そんなの知らないよ」と戸惑ったりするかもしれません。僕も最初はかなり動揺しました。
でも、そんなときこそ落ち着いて、まずは相手の話をしっかり聞くこと(傾聴)が何より大切です。怒りや不満の感情の裏側には、「誰かに話を聞いてほしい」「分かってほしい」という気持ちがあることが多いんです。
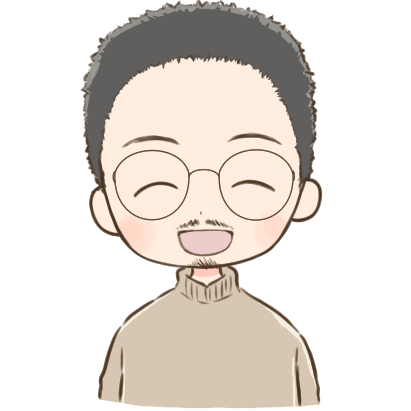
たとえすぐに解決できなくても、「聞いてくれた」「ちゃんと受け止めてくれた」と思ってもらえるだけで、安心される方もたくさんいます。
トラブル対応へのポイント
- 相手の話を最後まで遮らずに聞く
- 否定せず、「そうなんですね」と共感の姿勢で
- メモを取りながら聞くと、丁寧な印象に
- 解決策を無理に出そうとしなくてOK
そして何より大切なのは、一人で抱え込まないこと。
「自治会長なんだから、自分が何とかしないと…」と背負い込む必要はありません。
状況によっては、班長さんや他の役員、町内会全体で共有するべきこともありますし、騒音や敷地の問題など、行政や管理組合などの専門機関に任せた方が適切な場合もあります。

「これは市役所に相談してみましょうか」
「この件は管理組合にお願いしましょう」
そんなふうに、“地域の窓口役”としてつなぐ役割に徹するのも、立派な対応です。
苦情やトラブルは、たしかに気を遣う仕事ではありますが、丁寧に対応して信頼を得られるチャンスでもあります。焦らず、無理せず、ひとつひとつ、一緒に乗り越えていきましょう。あなた一人じゃありません。
一番の財産は「人とのつながり」
自治会って聞くと、どうしても「会議」「行事」「当番」みたいなやることリストばかりが頭に浮かびがちですよね。でも実際に関わってみると、そこにはもうひとつの大切な側面があるんです。
それが、人とのつながり。
地域の活動って、実はいろんな世代、立場、職業の人たちが、少しずつ時間や力を持ち寄って動かしているんですよね。普段の生活ではなかなか関わることのないご近所さんと顔を合わせて、「あ、○○さんってこんな人だったんだ」「意外と気さくな人だな」なんて新しい発見があったりします。
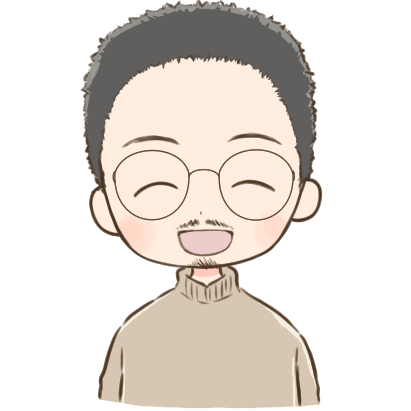
行事の準備を一緒にしたり、掃除の後に立ち話をしたり、たまにお茶を飲みながら昔話を聞いたり。そんな小さな交流が、いつの間にか地域への愛着や安心感に変わっていくんですよね。
地域って、建物や道路じゃなくて人でできているんだなと実感できたのも、この経験を通してでした。だからこそ、自治会活動の中で生まれる人とのつながりは、実はとても貴重な財産なんです。
完璧じゃなくても大丈夫。うまくやろうとしなくていい。ときには失敗してもいいんです。
無理せず、自分のペースで、できることを少しずつ続けていけば、1年後にはきっと「ちょっと成長したな」と思える自分に出会えるはずです。
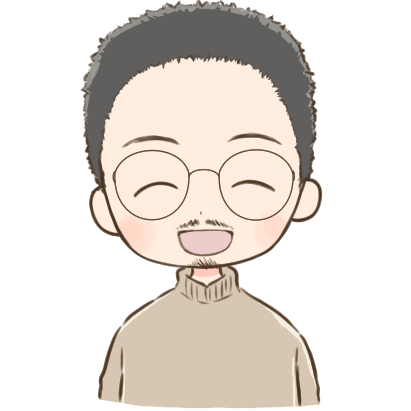
「自治会って、思ったより悪くなかったな」
そう思えたら、それだけでも大成功です。
「えっ、自分が!?」突然の自治会長の打診に、戸惑いや不安を感じた気持ち、本当によくわかります。僕もまさにその立場でしたし、「自分にできるのかな」「大丈夫かな」と思いながら始めた一人です。
でもね、不思議なことに、やってみると少しずつ見えてくるものがあります。
地域の雰囲気、人のあたたかさ、自分の中にあった“誰かの役に立ちたい”という気持ち。
そういうものが、じわじわと感じられるようになってくるんです。
最初から完璧じゃなくていいんです。
失敗したって大丈夫。誰かがきっと助けてくれます。
そして何より、あなたにしかできない「地域づくりのカタチ」が、きっとあるはずです。
肩の力を抜いて、自分らしく、一年を過ごしてみてください。
うまくいかない日もあると思いますが、そんなときはこのコラムのことを思い出してもらえたら嬉しいです。
「そうそう、あの人も最初は不安だったんだよな」って。
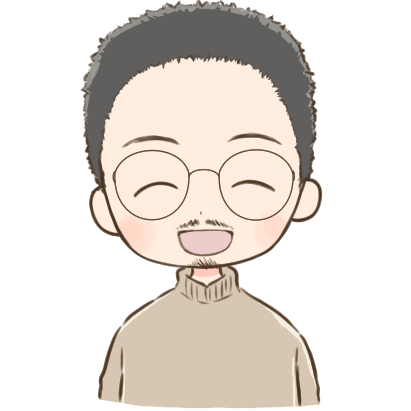
一人じゃありません。応援している仲間は、ちゃんといます。これからの一年が、あなたにとってちょっとだけ特別で、あたたかく、意味のある時間になりますように。応援しています!
このブログを読んでのご感想など
このブログ記事を読んでのご感想をお送りください。ブログを書く励みになったり、もしかすると読者からのメッセージとして記事で紹介させていただくこともあるかもしれません。お気軽にどうぞ。