2025年3月26日

新年度を迎えるこの時期、多くの自治会や町内会では新しい役員の選出が行われ、地域の運営体制が新たにスタートします。地域のつながりを大切にし、防災・防犯、行事の企画運営やゴミステーションの管理など、暮らしを支える活動に欠かせない存在である自治会や町内会。しかし最近では、役員の選出と並行して「退会したい」と申し出る住民が増えているという声も多く聞かれるようになりました。特に若い世代や共働き世帯を中心に、加入のメリットが見えにくい、役割の負担が重すぎる、人間関係のストレスが大きいといった理由から、加入を見直す動きが広がりを見せています。
こうした傾向は全国的にも共通しており、自治会や町内会の在り方そのものが、時代の変化とともに見直しを迫られているとも言えるでしょう。そこで、なぜ退会希望者が増えているのか、その背景や要因を探るとともに、今後どのような工夫や対策が考えられるのかを整理し、より多くの人にとって「参加してよかった」と思える自治会・町内会運営のヒントを僕自身2年間の自治会長を務めた経験を踏まえて考えていきます。
なぜ自治会や町内会を退会したい人が増えているのか?
自治会や町内会活動に参加する負担感の大きさ
自治会や町内会の役員は、年間を通して会議やイベントの準備、地域の取りまとめなど多岐にわたる業務を担います。そのため「仕事が忙しくて時間が取れない」「土日に休めない」といった共働き世帯や、「体力的にきつい」「理解が追いつかない」と感じる高齢者にとって、役員の負担は決して軽いものではありません。一度役員になると長期にわたって責任を負うケースもあり、精神的なプレッシャーも大きいのが現実です。そうした中で「無理してまで続けたくない」「次にまた役が回ってくるのが怖い」と感じ、退会を選ぶ人が増えているのです。
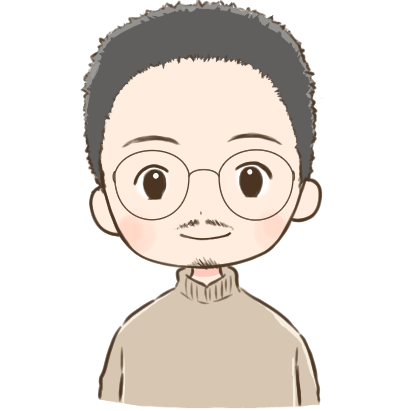
組長や班長が回ってくるタイミングで退会を希望される方が多いですね^^;
自治会や町内会活動の内容の不透明さ
自治会や町内会に加入していても、日常的にその活動の全容を把握している住民は意外と少ないものです。「何をしているのかよくわからない」「会費を払っているけれど、その使い道が見えてこない」といった疑問を持つ人が増えています。広報が行き届いていなかったり、参加者だけで物事が進んでいるように見えると、非加入者との温度差も広がっていきます。結果として、「よくわからないものにお金や時間を使いたくない」と感じる人が退会を考えるきっかけとなっているのです。透明性の欠如は、信頼の低下にも直結します。
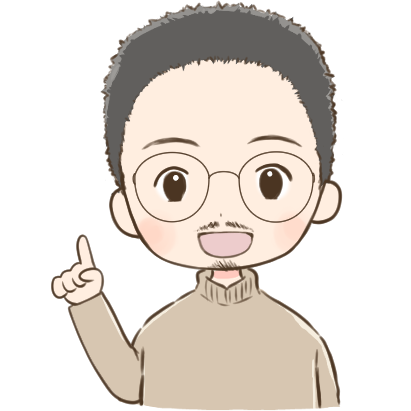
回覧板もほとんど見ない住民も多いので余計に何をしてるかわからないって思われます。僕も自治会長やるまでは回覧板なんてほとんど見ませんでしたから(笑)
自治会や町内会の中でのプライバシーや人間関係への不安
かつては地域のつながりが防犯や安心感につながっていましたが、現代ではその人間関係を「負担」と感じる人が増えています。回覧板での情報共有、近所付き合い、挨拶や訪問のやりとりなどが「煩わしい」「干渉されている気がする」と受け取られてしまうことも。さらに、役員同士のトラブルや会合での発言に対する不満など、内部の人間関係に疲弊し、距離を置きたくなる人もいます。そうした心理的ストレスが、退会を後押しする要因になっているケースも多く見受けられます。
自治会や町内会は任意加入であるという事実の浸透
インターネットやSNSを通じて「自治会や町内会への加入は任意である」という情報が広まり、加入を当然とする価値観に変化が生まれています。特に若い世代を中心に、「強制されるものではないなら、無理に参加しなくてもいいのでは」と考える人が増加。また、自治会に加入していなくても行政サービスやゴミの収集は受けられるため、加入の必要性を感じにくいという実情もあります。義務感から参加していた住民が「選べるならやめよう」と思うのは、時代の流れとも言えるでしょう。

かつてPTA不要論が言われたように今では自治会や町内会に同じ論調が見受けられます。PTAの時もそうでしたが自治会や町内会がなくなるのは困ることも結構あると思うんですけどね。
自治会・町内会側の困りごと
住民の退会が増えると、まず直面するのが会費収入の減少です。自治会や町内会はその会費をもとに、防犯灯の電気代、清掃用具の購入、行事の運営費、防災備蓄品の整備など、地域の安全や快適な生活環境を維持するための活動を行っています。退会者が増えれば、こうした活動に必要な予算が不足し、イベントの縮小や中止、防犯灯の間引き設置、防災体制の弱体化といった影響が出かねません。
また、ゴミステーションの清掃・管理や回覧板の配布など、誰かがやらなければならない作業の担い手が減るため、残った役員や会員の負担が一層重くなります。これが原因でさらに辞退者が増えるという悪循環に陥る恐れもあり、自治会や町内会の継続的な運営が難しくなるという深刻な課題につながっています。
自治会や町内会の退会者を減らすためにできること
自治会や町内会役員の負担軽減
退会を防ぐためには、まず役員にかかる負担を減らす工夫が必要です。現在の体制では、限られた人数で多くの仕事をこなさなければならず、それが敬遠される大きな要因となっています。そこで、役割を細かく分担したり、短期間の当番制を導入したりすることで、負担の分散が図れます。また、議事録の作成や回覧物の印刷・配布など、一部の業務を外部委託するのも有効な方法です。役員が「これなら無理なくできる」と思える仕組みを整えることで、参加への心理的ハードルが下がり、退会の抑止につながります。
自治会や町内会からの情報発信と見える化
自治会や町内会が何をしているのか、住民にきちんと伝わっていないことが退会の一因になっています。活動内容や会費の使い道を定期的に広報し、誰でも確認できるようにすることが重要です。回覧板だけでなく、掲示板や地域のLINEグループ、SNSなど、複数の手段で情報発信を行いましょう。「何のために」「誰のために」行っているのかを丁寧に伝えることで、理解と納得が得られます。見える化は、自治会への信頼感を高め、無関心層の参加意識を刺激するきっかけにもなります。
自治会や町内会への柔軟な参加の仕組み
「すべての活動に参加しなければならない」という固定観念が退会につながっている場合もあります。そこで、できる範囲だけでも協力できる「ゆるやかな参加」の仕組みを整えることが大切です。たとえば、イベント時だけの手伝いや、特定の得意分野での貢献など、選択肢を増やすと参加しやすくなります。また、会議をオンラインで行ったり、資料をデジタル化したりすることで、参加の負担を軽減できます。多様なライフスタイルに対応した柔軟な運営は、今後ますます求められていくでしょう。
自治会や町内会に参加することのメリットを明確に伝える
自治会・町内会のメリットが伝わっていないと、加入の意義を見いだせずに退会されてしまいます。そこで、防犯灯の設置や防災訓練、地域イベントなど「住んでいて安心・楽しい」と感じられる具体的な活動を積極的に紹介しましょう。たとえば、「自治会のおかげで不審者の侵入が防げた」「災害時に情報がすぐ届いた」といった実例を伝えることで、参加の意義が明確になります。会員の声や体験談を通して、「入っていてよかった」と思えるような前向きなイメージを広げることが、退会防止には効果的です。
退会者を減らすためのポイント
- 役員の負担軽減
- 仕事を分担し、短期の当番制を導入する
- 一部業務を外部委託し、無理のない体制を整える
- 情報発信と見える化
- 活動内容や会費の使い道を定期的に知らせる
- SNSや掲示板などで目的をわかりやすく伝える
- 柔軟な参加の仕組み
- イベント時だけの参加や得意分野での協力を歓迎
- 会議のオンライン化などで負担を軽減する
- 参加メリットの発信
- 防犯・防災・交流などの具体例を紹介する
- 「入ってよかった」と思える声や体験談を共有する
退会希望者への対応で気をつけたいこと
自治会や町内会に退会の申し出があった際、対応する側が気をつけたいのは、感情的にならず、相手の話に丁寧に耳を傾ける姿勢です。長年活動してきた立場からすれば、退会の申し出に対して寂しさや戸惑い、場合によっては怒りの感情が生まれることもありますが、そこで相手を非難したり、無理に引き止めようとしたりするのは逆効果です。むしろ、なぜ退会を希望するのか、その背景にある不満や悩みを冷静に聞き取ることで、自治会や町内会の運営改善につながる大きなヒントが得られることもあります。
例えば、「役員の仕事が大変すぎた」「活動内容がよくわからなかった」「特定の人との関係がつらかった」といった声があれば、それに対応する工夫や見直しを図ることができるでしょう。また、「去る者は追わず」というスタンスを取るよりも、「なぜ去るのか」を真摯に見極める姿勢を持つことが、今後の運営において非常に重要です。
一人の退会には、組織として見直すべき課題が隠れているかもしれません。丁寧な対応は、たとえその時に退会を止められなくても、「あの自治会はちゃんと話を聞いてくれる」との印象を残し、将来的な再加入や他の住民への良い影響にもつながります。
持続可能な自治会・町内会活動
自治会や町内会は、防災・防犯、環境美化、地域交流など、住民の安全で快適な暮らしを支える重要な役割を担っている組織です。普段あまり意識されることは少なくても、災害時の助け合いや、ゴミステーションの整備、防犯灯の維持といった日常の安心は、こうした地域活動に支えられています。
しかし近年、退会を希望する住民が増えているのは、単なる無関心ではなく、ライフスタイルや価値観の多様化、負担の重さ、情報の不足など、時代の変化に組織運営が追いついていないことの表れとも言えます。これは決して悲観すべきことではなく、運営のあり方を見直し、「参加してよかった」「無理なく続けられる」と思ってもらえる自治会・町内会に生まれ変わるチャンスと捉えるべきです。
役員の負担を減らし、情報をきちんと伝え、柔軟で開かれた参加の仕組みを整えることが、信頼の回復と参加意欲の向上につながります。地域社会が希薄になりつつある今だからこそ、誰もが気持ちよく関われる自治会・町内会のあり方を考えることが、これからの持続可能な地域づくりへの第一歩となるのです。
このブログを読んでのご感想など
このブログ記事を読んでのご感想をお送りください。ブログを書く励みになったり、もしかすると読者からのメッセージとして記事で紹介させていただくこともあるかもしれません。お気軽にどうぞ。