2025年3月23日

豊橋市で進められてきた「豊橋新アリーナ建設計画」は、豊橋市の新たなランドマークとして期待する声もある一方で、豊橋市民の間では賛否が分かれています。これまで豊橋新アリーナ建設推進派の方々は、アリーナを整備することでBリーグの三遠ネオフェニックスのホームアリーナとしての活用やコンサートやライブなどの大型イベントの開催が可能になり、豊橋駅から豊橋公園の間のにぎわい創出につながると主張してきました。加えて、災害時には避難所としても活用できるなど、多目的な機能を持つことが利点とされています。
たしかに、こうした意見には一理あります。豊橋新アリーナが完成すれば、目に見える形で豊橋市のまちなかの活力を象徴する存在になるかもしれません。しかし、本当に今、豊橋市民の憩いの場である豊橋公園にそのような大型施設を新たに建設する必要があるのでしょうか?豊橋市の財政状況や人口減少、高齢化といった課題を前にしたとき、その必要性には疑問が残ります。
昨年11月には新たな豊橋市の市長として長坂尚登氏が初当選し、就任以降この新アリーナ計画についても「新アリーナ建設中止の手続き」が進められています。豊橋市民からの意見や予算の妥当性、既存施設の活用可能性など、これまで十分に議論されてこなかった側面に光が当てられ始めた今こそ、立ち止まって考える絶好のタイミングです。
今回は豊橋新アリーナ建設に反対する立場から、豊橋新アリーナ建設に反対する根拠を整理し、豊橋市民一人ひとりが「本当に必要な公共事業とは何か?」を考えるきっかけとなることを目指します。未来の豊橋のために、今こそ冷静な議論が求められています。
豊橋新アリーナ建設計画の現状と背景
豊橋市が進めている新アリーナ建設計画は、総事業費約230億円を投じ、豊橋公園東側エリアに多目的屋内施設を整備するプロジェクトです。当初の計画では、2027年の開業を目指していました。
しかし、昨年11月の市長選挙で新アリーナ計画の中止を公約に掲げた長坂尚登氏が当選し、就任後、計画の見直しが進められています。これに対し、豊橋新アリーナ建設計画の継続を求める市民から約13万4000筆の署名が集まり、市議会に提出されましたが、市長は「選挙の結果を尊重する」として、契約の継続は検討しない意向を示しています。
豊橋市の人口は2009年をピークに減少傾向にあり、少子高齢化が進行しています。こうした状況下での新アリーナのような大型施設建設には、市の財政負担や将来的な利用需要に対する懸念の声も上がっています。
これまでの豊橋市内のスポーツ施設整備においても、老朽化した既存のスポーツ施設の集約や再整備が課題とされてきました。新アリーナ計画は、こうした課題解決の一環として位置づけられていましたが、現在は計画の是非をめぐり、市民や議会内で活発な議論が続いています。
今後の動向次第では、豊橋市のまちづくりや財政運営に大きな影響を及ぼす可能性があり、市民一人ひとりが関心を持ち、議論に参加することが重要とされています。
市民の意見が十分に反映されていない
新アリーナ建設に関してもうひとつ大きな問題として挙げられるのが、「市民の声が十分に反映されていない」という点です。豊橋市はこれまでに何度かパブリックコメントの募集や住民説明会を行ってきたとされていますが、その実態を見ると、参加者の数はごくわずかで、内容も限定的だったという印象を受けます。
市が実施したパブリックコメントには、計画に反対または慎重な立場を取る意見も多く寄せられました。しかし、これらの声が計画にどのように反映されたのか、その過程は市民にとって非常に見えにくいものでした。「意見を聞いたふり」で終わっていないかという不信感が、少なからず広がっています。
新アリーナ建設に関する住民説明会に関しても同様です。事前に十分な周知が行われていなかったり、質疑応答の時間が限られていたりと、市民が主体的に参加できる場にはなっていなかったという指摘もあります。また、資料の公開が遅かったり、専門用語が多くて理解しづらかったりするケースもあり、「形式的な手続きにとどまっていたのではないか」との疑念を拭えません。
そもそも、230億円という巨額の税金を使う計画であるにもかかわらず、それが一部の関係者や有識者の間だけで進められていたとすれば、豊橋市政のあり方として大きな問題です。市民が本当に望んでいるのは何か、市民一人ひとりの暮らしにどう影響するのか?そうした視点が計画の根底に欠けていたのではないでしょうか。
昨年の豊橋市長選で「計画の見直し」を掲げた候補が当選した事実は、まさに「豊橋市民の声が届いていない」という現状への強い不満の表れです。今こそ、市政は市民の意見を真正面から受け止め、丁寧で開かれた対話の場を作り直すべきではないでしょうか。
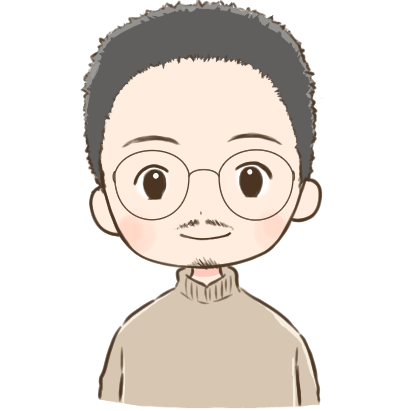
建設計画が進んでいる間はあんまり説明会を開かなかったのに、計画中止の流れになったとたん建設推進派の市議会議員が説明会を開催するところが何だかねww
利用実態と整合しない規模・用途
豊橋新アリーナ建設計画に対して疑問の声が上がる理由として、現在の利用実態と計画されているアリーナの規模・用途が釣り合っていない点が挙げられます。豊橋市内にはすでに総合体育館や各地区のスポーツ施設があり、現在でも大会や練習など多様な目的で利用されています。しかし、それらの施設が「足りない」と感じるほど利用が逼迫しているというデータや報告は限定的です。
市の施設予約状況を見ても、時間帯によっては空きがあり、すべての市民が利用機会を奪われているというわけではありません。にもかかわらず、約5,000人規模ともいわれる新アリーナの整備が進められようとしているのは、本当に「市民のニーズに基づいた判断」なのでしょうか?
また、「プロスポーツや音楽イベントの誘致」「交流人口の増加による経済効果」などの理由も挙げられていますが、これらの根拠は本当に現実的なものでしょうか?すでに多くの自治体が同様の目的で大型アリーナを建設していますが、期待通りの集客や収益につながっていないケースも少なくありません。近隣の豊田市や名古屋市などにはすでに大規模な会場があり、競合も多い中で、豊橋だけが継続的に大型イベントを誘致し続けられる保証はどこにもありません。
一時的なにぎわいや注目度を過大評価し、実際の市民生活とはかけ離れた新アリーナを建ててしまえば、それは「箱モノ行政」の典型です。市民の生活に密着した施設整備こそが求められているにもかかわらず、大規模かつ不確実性の高いプロジェクトに多額の税金を投入することは、将来的に重い負担となって跳ね返ってくる可能性があります。
今必要なのは、見栄えの良い夢の施設ではなく、地に足のついた現実的なまちづくりではないでしょうか。
他自治体のアリーナ建設における失敗事例
青森市の複合施設「アウガ」の経営破綻
青森市は、中心市街地の活性化を目的に、2001年にJR青森駅前に複合商業ビル「アウガ」を開業しました。 地下1階・地上9階建てのこの施設には、商業テナントや公共施設が入居し、約185億円を投じて建設されました。 しかし、開業初年度の売上は目標の52億円に対し、実際には23億円と大きく下回りました。 その後も経営は改善せず、2015年度には約24億円の債務超過に陥り、最終的に市庁舎として再利用されることとなりました。
さいたまスーパーアリーナの赤字運営
さいたま市の第三セクターが運営する「さいたまスーパーアリーナ」は、2003年に6億6,000万円の赤字を計上しました。 その後、事業計画や運営体制の見直しが行われましたが、当初の計画段階での需要予測や収支計画の甘さが指摘されています。
「箱物行政」の問題点
これらの事例は、いわゆる「箱物行政」の問題点を浮き彫りにしています。 すなわち、施設の建設そのものが目的化し、地域住民のニーズや実際の利用状況を十分に考慮しないまま進められた結果、維持管理費が財政を圧迫し、最終的には地域の負担となるケースが多いのです。 バブル時代には各地で公営水族館が建設されましたが、設備の寿命が30年とされる中で景気後退により修繕費が捻出できず、2020年ごろから閉園が相次いでいる例もあります。
豊橋に本当に必要なものとは?
これまで見てきたように、豊橋市の新アリーナ建設計画には多くの課題と疑問点が存在します。では、豊橋市に今、本当に必要なものとは何なのでしょうか。大切なのは「規模」や「華やかさ」ではなく、持続可能で、市民一人ひとりの生活に寄り添ったまちづくりではないでしょうか。
まず第一に考えるべきは、既存施設の有効活用です。市内には総合体育館をはじめ、地域ごとに体育施設や文化施設が整備されています。これらの中には老朽化が進んでいるものもあり、改修や機能改善の必要がありますが、逆に言えば、それだけで市民の活動の場を守り、支えることができるということでもあります。新たに巨額の資金をかけて建物を「一からつくる」よりも、限られた財源の中で「あるものをどう活かすか」という発想が、今の豊橋にはふさわしいのではないでしょうか。
次に求められるのは、「コンパクトで持続可能な都市」への転換です。人口減少と高齢化が避けられない中、むやみに都市機能を拡大するのではなく、既存の資源を効率よく使い、小回りの利く地域づくりを進めていくことが求められます。大型施設を建てても、それを将来的に支える利用者も税収も先細る現実を直視すべきです。
そして何より大切なのは、豊橋市民の声が反映された予算配分です。教育や福祉、医療、防災といった身近な暮らしに直結する課題に対して、どれだけの税金が使われているかを見直すべき時期に来ています。市政は豊橋市民の声を聴き、その声に応じてお金を使うべきです。
派手な施設よりも、静かに暮らしを支える施策のほうが、長い目で見て豊橋市民の幸福につながります。いま必要なのは、目に見えるモノよりも、目に見えにくい安心やつながりを育てるまちづくり。その視点で未来の豊橋を描いていくことが、私たちにできる最も現実的で責任ある選択ではないでしょうか。
このまちに住む私たち自身が、「どうありたいか」を選ぶとき
これまで述べてきたように、豊橋市が進めてきた新アリーナ建設計画には、財政への過度な負担、市民参加の不足、実態と合わない用途設定など、多くの懸念材料があります。夢や期待を否定するつもりはありませんが、現実を見据えた冷静な判断が今こそ必要です。
一度立ち止まり、ゼロベースで計画を見直す勇気が、豊橋の未来を守ることにつながります。私たちは行政の決定をただ受け入れるだけの存在ではなく、声を上げ、方向を変える力を持っています。昨年の市長選で「見直し」を掲げた候補が当選したことも、その意思の現れです。
豊橋市民一人ひとりが関心を持ち、「本当に必要なのか?」「他に優先すべきことはないのか?」と問い続けることが、健全な市政を育てます。職場で、家庭で、学校で。身近な人と話すことも立派な第一歩です。そして、もしあなたの中に「おかしい」「納得できない」という気持ちがあるなら、それを行動に変えてみませんか?
このブログを読んでのご感想など
このブログ記事を読んでのご感想をお送りください。ブログを書く励みになったり、もしかすると読者からのメッセージとして記事で紹介させていただくこともあるかもしれません。お気軽にどうぞ。